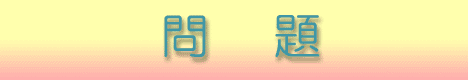
★★★完全パンクマニュアル発売中です!〈amazonで購入〉★★★
| ●SS「手塚の恋」 |
|
一、 少年は、緊張した面持ちで扉の前に立っていた。 ――何事も最初の印象が大切だ 夏の熱気も治まり、もうじき初秋を迎えようという時期である。 少年は新しいクラスメートとの出会いに、楽しみよりも、遥かに不安を覚えていた。 ――果たして、この学校は自分を受け入れてくれるのだろうか 教室の中から自分を呼ぶ先生の声が聞える。 少年は意を決して扉を開けた。 「えー、このたび、二学期からみんなのクラスメートとなる手塚国光くんだ。事情があって我が校へ転校してきたらしい。みんな、仲良くするように」 先生から紹介を受け、少年は口を開く。 「手塚です。みなさん、よろしく」 「イェーイ! ヅカちゃーん!」 クラスの奥の方から男子生徒の陽気な声が聞え、クラス中に哄笑が起こる。 彼はきっとクラスでもお調子者の生徒なのだろう。 初対面の転校生にいきなりニックネームで呼びかける辺りからそれが伺える。 普通の転校生なら、もしかすると彼の馴れ馴れしさにムッとしたかもしれない。 しかし、手塚にはみんなのそんな反応も嬉しかった。 耳を澄ませば、幾人かの女子生徒のひそひそ声も聞える。 「ねえ、手塚クンって結構カッコイイんじゃない?」 「COOLな感じがするよね、COOL!COOL!」 ――この学校なら、上手くやっていけるかもしれない 手塚はふとそんなことを考えたが、すぐに打ち消した。 最初はどこの学校だって大丈夫なんだ……。問題はこれからだ……。 「えー、それで、我が校は勉学だけではなくスポーツにも力を入れていて、各種運動部も充実している。手塚君、きみも部活に入らないかね? ちなみに、手塚君は中学の時は何のスポーツをしてたのかな?」 「ヅカちゃーん! オレと一緒にバスケしようぜー!」 クラスにまた哄笑が起こる。 壊したくない。この幸せで微笑ましい世界を破壊したくない。 でも、自分を偽って生きることもできない。 今言わなくてもいつかは絶対に分かってしまうことなのだ。 「野球とかやってそうだよな…」 「意外と手芸部とかだったりしてね、キャハ」 ざわざわと無責任な噂で盛り上がるクラスメート。 一瞬の間を置いて、手塚はついにそのことを告げた。 「中学では…………テニスをしていました」 水を打ったように静まり返るクラス。 みんなが手塚を一瞬凝視しすぐに目をそらした。 先ほどまで調子に乗っていた男子生徒も、頭を抱え、机にうっぷしブルブルと震えている。 ここも、同じだったか―― 手塚の表情に悲哀の色が差し込む。 先生も手塚から後ずさりして距離を離し、手塚の機嫌を伺うように上目遣いで見ている。 「ま、まあみんな、落ちつけ…。テニスプレイヤーといっても色々だ。全国に出るようなプレイヤーもいれば、帰宅部に程近いプレイヤーまでいる。て、手塚君、きみは中学の時はどのくらいテニスをやっていたのかな? たとえば、大会とか……」 ここまで来ては、もう隠し立てをしてもどうしようもないだろう―― 諦念の気持ちで手塚は全てを語った。 「テニスは……全国大会まで行きました。青春学園で部長もしていましたし、オレは今でもテニスをしていたことを後悔していません」 手塚の告白にクラスはふたたびざわついた。 「ぶ、部長……」 「全国だって…!」 みんなが汚いものを見るような目で手塚を見ている。 ――いつもこうだ。オレはどこでだって…… 「じゃ、じゃあ、て、手塚くん、きみの席は、その後ろの藤原と横井の間で……いいかな? あの、もし席が気に入らなかったら、言ってくれないかな。便宜は図るから……」 先生が慌ててまとめに入る。 一刻も早くこの場から逃げ出したいのだろう。 顔色からありありと分かる。 手塚もこんな居心地の悪い立ち位置は早く終わらせたかった。 教壇に立っていては、針のむしろである。 「いえ、結構です。ありがとうとございます、先生」 「で、では、私は次の授業の準備があるので! みんな手塚くんと仲良くするように!」 先生は急いで荷物をまとめて、早足で教室から出ていった。 「クソッ、一人だけ逃げやがって……」 「あれでも教師かよ……」 クラスメートたちは、机に目を伏せたまま先生の卑怯な行いを小声で糾弾した。 手塚が指定された席へと近づく。 すると、横の席にいた生徒、藤原がビクッと身体を硬直させ、さらに一層身体を震わせて手塚を見上げた。 先ほどまで手塚をヅカちゃんと呼んで笑っていたお調子者の男子生徒である。 「や、やあ。あの、さっきはご、ごめん……。あの、て、手塚くんがテニスプレイヤーだったなんて、知らなくて。あの、知らなくて済まされることじゃないとは分かってるけど……」 手塚は震えるクラスメートを少しでも安心させようと、いつもは能面のようなその表情を無理矢理笑顔に変えて微笑んだ。 「ヒ、ヒィィィイイ!!!!!!」 だが、その無理な笑顔は逆効果だったようだ。 手塚の作り笑いを見た藤原は、恐怖のあまり椅子から転げ落ち、尻餅を付いた後、脱兎のように駆け出し教室から逃げていってしまった。 やっぱり、オレには無理なのかもしれない――手塚は人知れずため息を漏らした。 ニ、 休憩時間に入ってもクラスの重苦しい雰囲気に変わるところはない。 誰一人として手塚に話しかけようとする者はおらず、みな手塚から距離をおき、ブツブツと小声で陰口を叩いている。 「クソッ……なんでテニスプレイヤーがうちみたいな普通の高校に……」 「氷帝高か立海大付属高へ行けばいいのによ……」 「てか、あいつ、青春学園だろ。あそこ確か高等部あったんじゃないか?」 「しかも『テニスをしていたことを後悔していない』だってよ。悪びれもしてねえよ」 「何にせよ迷惑な話だぜ。テニスプレイヤーなんて入ってきたら勉強できねえじゃねえか、できねえよ」 彼らの陰口は昼休憩に入る頃には、さらに加熱していた。 「おい、D組のやつから聞いたぜ。あの手塚ってやつ、テニスで対戦相手を精神崩壊させたことがあるんだってよ」 「私も聞いたんだけど、船を一隻沈められるくらいのテニスらしいわ」 「マジかよ。じゃあもし怒らしたら、オレたちなんて跡形も残らねえじゃねえか」 「何にせよ関わらない方が身のためだな……」 「それに、テニスプレイヤーって人の心の中を読めるらしいからな」 「うわっ、マジで。キモっ!」 「やだっ!あたしたち、こんなこと話してるのもバレてるんじゃないの!?」 いつもこうだった。 どこの学校にいっても同じだ。 いつもみんなは手塚がテニスプレイヤーというだけで差別した。 誰も対等には扱ってくれなかった。 ――こんなことなら、やっぱり不二や菊丸たちと一緒に高等部に進めば良かった 手塚は悔恨の念に駆られた。 高校でも一緒にテニスをやろう――そう言ってくれた不二や菊丸たちを手塚は裏切った。 一つは、普通の高校生として高校生活を楽しんでみたいという気持ちもあった。 もう命がけのバトルはご免だった。 手塚の実力なら世界大会やプロになることも可能だっただろう。 だが、その果てに何があるのか。 どれほど実力のあるプロ選手でも、3年も生き延びられないのがプロの世界だ。 運良く致命傷を負う前に引退できればいい。 だが、ほとんどの選手は試合中に命を落としている。 手塚はもっと普通の安穏とした人生を送りたいと考えていた。 人を殺すのも、殺されるのも、もうたくさんだ―― 中学3年間をテニスに捧げた手塚の、それが正直な気持ちだった。 それに、人並みの恋もしてみたかった。 テニスプレイヤーの恋は、恋といえるようなものではない。 彼らにとっての女とは、人ですらない。 たとえば女は、賭けテニスによって得る賞品であったりする。 またあるときは、敵のテニス部が送りこんでくるスパイである。 跡部などはそこらを割り切って楽しくやっているが、手塚にはとてもそんな気持ちにはなれなかった。 彼は愛し愛される普通の恋愛を望んでいたのだ。 ――手塚、そんなことが許されると思っているのか? そう不二はいった。 ――手塚は甘いよー。オレたちテニスプレイヤーがテニス以外の世界で生きていけるわけないのに。 菊丸もそう言っていた。 ――うぉぉぉガッデム!バーニング! ラケットを持った河村は何を言っているのか分からなかった。 ――不幸になる確率……100% 乾……お前のデータ、また当たったかもしれない…… 三、 だが、放課後、悲嘆に暮れる彼の前に一人の少女が立った。 「手塚くん、良かったら、あたしと一緒に帰ろ?」 隣の席の女子、横井美佳である。 特別に可愛らしい少女ではない。むしろ腫れぼったい瞳には野暮すら感じる。 だが、小柄な顔立ちと、手塚に微笑みかけたその笑顔は、悲しみに満ちた少年の心を魅了するには十分だった。 「きみの申し出は大変ありがたい。しかし、いいのか? オレはテニスプレイヤーだったんだぞ」 「うん、大丈夫だよ。みんな怖がり過ぎだよね。テニスプレイヤーだっていろいろいるって知ってるもん。手塚くんはそんなコワイ人じゃなさそうだし」 少年と少女はしばしの間見詰め合って微笑み、そして、荷物をまとめて二人して教室を出ていった。 残されたクラスメートたちは、手塚が教室を出て行ったことにホッと胸を撫で下ろしながらも、美佳の愚行を嘆いた。 「美佳……どうしてあんなことを……」 「ちょっと男子! 美佳をあんな目に遭わせていいの!? 美佳はみんなの身代わりになって手塚と出ていったのよ! 誰か助けなさいよ!」 しかし、男子はみな震えて下を向くばかりである。 みな手塚のテニスが恐ろしいのだ。 「そ、そんなこと言ってもなぁ……」 「相手がテニスプレイヤーじゃ……かないっこないし……」 煮え切らない男子と、その態度にいらだつ女子。 だが、その中に一人、拳をわなわなと振るわせ、怒りに燃える少年がいた。 斉藤和也、美佳の幼馴染である。 「バカヤロー!美佳をほっとけるかよ!」 一声そう叫ぶやいなや、彼はカバンも持たずに教室を飛び出していった。 四、 「頭上注意」そう書かれた工事中のビルを横目に、二人は楽しく談笑しつつ帰路を歩いていた。 手塚にとって、それは久しぶりの普通の人間との触れ合いであった。 何気ない普通の会話、普通に笑い、普通に驚く。 そんな普通のことが、彼にはとても新鮮だった。 青春学園にいた時、彼はとてもこんなふうに笑うことはできなかった。 そこから抜け出し、ようやく普通の世界に飛び出したのに、そこに待ち受けていたのは差別と軽蔑の怨念渦巻く青春学園以上の地獄だった。 美佳に出会い、手塚は初めて「普通の日常」を手に入れた気がした。 ――天国でなくてもいい。この「普通」が、オレにとっての天国なのだから。 だが、彼らの一時の安息も、背後から近づく荒々しい足音にかき消されることになる。 「手塚ッ! 勝負だ! オレと勝負しろ!!」 「カズヤちゃん!」 先ほど教室を飛び出した斉藤和也が、ついに二人に追いついたのだ。 「待って、カズヤちゃん! 私、手塚くんに無理にさらわれたわけじゃないよ! 二人で一緒に帰っていただけなの!」 「もういい。無理をするな、美佳。お前をテニスプレイヤーなんかに渡すものか! オレが、死んでもお前を守る!」 和也は完全に我を忘れて、ただ手塚への怒りに駆られていた。 しかし、彼を責めることもできないだろう。 普通、テニスプレイヤーが女の子と一緒に歩いていれば、誰が見てもそれは女を無理矢理にさらったようにしか見えないのだから。 テニスプレイヤーに恋や愛などという感情があるとは誰も考えもしないことであった。 「手塚ッ! オレと戦え! 美佳を手に入れたいなら、オレを殺してからにしろッ!」 そういって、和也は手塚に殴りかかった。 和也の一撃を受け、地面に倒れこむ手塚。 倒れた手塚に馬乗りになり、和也がさらに拳を振るう。 ビシッ! ドカッ! 和也の拳が何度も手塚の頬を打つ。 だが、手塚に常人のパンチなど効くはずもない。 「どうした手塚! オレを舐めてるのかッ! お前がその気になればオレなんかすぐに殺せるだろ! だが、オレを殺しても美佳の心まではお前のものにはならない! オレを殺そうと、美佳を殺そうと、誰もお前の言いなりになんかならないぞ!」 「もうやめて、カズヤちゃん! 手塚くんはそんな人じゃないの! 誤解なの!!」 だが、美佳の必死の説得も興奮したカズヤには届かない。 手塚は頬を張られながらも困惑していた。 打撃はちっとも痛くはなかったが、心は痛かった。 せっかく美佳と仲良くなれたのに……ここで和也を殺すことは簡単だが、しかし、それでは美佳の心が…… 思うままに力を揮えぬこの状況に、手塚は為すすべもなく困惑するしかなかった。 そうして、およそ5分も殴られた頃だろうか。 興奮の極みにあった和也もさすがにおかしいと思い始めていた。 「どうした! 手塚! なぜ反撃してこない!」 「カズヤちゃん、いい加減気付いてよ! 手塚くんはそんな人じゃないって言ったじゃない! 手塚くんは無闇に人を傷つけるようなテニスプレイヤーじゃないのよ!」 美佳の言葉に和也が拳を止めた。 「ま、まさか……。手塚、お前は、本当に……」 と、その時である。 今まで殴られ放題好き勝手にやられていた手塚が、馬乗りになっていた和也を突然突き飛ばした! 手塚の豪腕に突き飛ばされた和也は10メートルも吹き飛ばされ、したたかにコンクリート壁に叩きつけられた。 「ぐあっ、クソ! 手塚やっぱりお前は……」 和也がそう言って手塚の方を向いた時、突然目の前に巨大な鉄柱が数本降り注いだのである! 鉄柱は轟音を立てて、先ほど和也と手塚がいた場所に積み重なった。 もうもうと砂煙が舞う。 和也は驚いて頭上を見上げ、全てを悟った。 工事中のビルから鉄柱が落ちたのだ! ――クソッ!頭上注意ってこういうことかよッ! 手塚に突き飛ばされなければ…オレはぺしゃんこに…… そこまで考えて和也はハッと気付いた。 「手塚……まさか、あれは、オレを庇って……手塚! 手塚ァー!!!!!」 和也が手塚を救出すべく慌てて駆け寄った。 美佳も泣きながら後へと続く。 二人とも手塚の生存は絶望的だと考えていた。 いくらテニスプレイヤーといえども、これほどの事故に遭い生きていられるはずがない……。 だが、噴煙は晴れてゆき、そこで二人は驚くべき光景を目の当たりにしたのである。 降り注いだ鉄柱は全て折れ曲がり、その中心で手塚がただ片腕一本で全ての鉄柱を支えていたのである。 鉄柱を防いだ手塚の左腕は、金色のオーラに包まれて神々しい光を放っていた。 「百錬自得の……極み」 手塚は、鉄柱をゆっくりと地面へ下ろした。 五、 「すまねえ、手塚! オレは本当に、申し訳ないことをしてしまった……」 美佳から事情を聞いた和也は、さっきから平謝りに謝っている。 「いや、気にしないでくれ。オレのことなら問題はない」 「だ、だがッ……!」 確かに手塚にほとんどダメージはなかっただろう。 「だが! オレの気持ちが収まらねえんだ! お前には酷いことをしてしまった……。人を見かけで判断して……。頼む! オレを殴ってくれ! 思いっきり殴ってくれ! そうしねえと、オレの納得がいかねえんだ!」 「バカ! カズヤちゃんのバカ! 手塚くんにこれ以上殺人を重ねさせる気なの!? 彼はもうテニスをやりたくないって言ってるのよ! カズヤちゃんなんか手塚くんのパンチ一発で跡形もなく吹き飛ぶのよ!」 「分かってる! 分かってるけど、オレが納得がいかねえんだ!!」 和也は泣きながらそう叫んだ。 その姿を見て、手塚が和也の肩を叩く。 「よし、和也。歯を食いしばれ。お前の言う通り、一発だけ殴らせてもらう。それで今回のことはお互い水に流すぞ。分かったな?」 「そんな……手塚くんまで何言ってるの! カズヤちゃんやめて! カズヤちゃんが死ぬのも、手塚くんが人を殺すのも、私見たくない!」 「おう、やってくれ! 一度はあんたに救われた命だ! あんたに奪われるなら悔いはねえ!」 手塚が大きく拳を振りかぶる。 「いくぞ……目を閉じてろ……」 「やめて―――!!!!!」 美佳の絶叫が響いた。 だが、手塚は振りかぶった拳をゆっくりと開き、軽く和也の額にデコピンをしただけだった。 「て、手塚……お前……」 「フッ、これで一発。約束は約束だぜ、カズヤ?」 「手塚くん…………!」 空に夕闇の帳が降りるころ、三人は高らかに笑いあった。 六、 「手塚……ごめんな。オレもみんなと同じでお前のことを誤解してた。テニスプレイヤーってのは、みんな同じだと思ってたんだ。お前みたいなやつもいたんだな……」 「ああ、確かにテニスプレイヤーは強大な戦闘力を持っている。好戦的なヤツも多い。でも、みながみな望んで戦いに赴くわけじゃないんだ。戦うことが嫌いなやつだって、もちろんいる。そこを……分かってくれ」 3人は帰り道を歩きながら、語り合っていた。 3人とも十年来の親友のような打ち解けた雰囲気である。 あの一件がなければ、これほどまで心の置けない仲にはなれなかっただろう。 まさに雨降って地固まるである。 「手塚……オレからもみんなに話してみるよ。みんな悪いやつじゃないんだ。ただ、ちょっとテニスという言葉に怯えてるだけなんだ。きっと、話せば分かってくれる……」 「あたしもみんなに話してみる。すぐには無理だと思うけど、でも、みんなきっと分かってくれると思うんだ」 「和也……美佳……でも、お前たちまでみんなから……」 「大丈夫だって。みんなイイやつなんだからさ、ホントは。それにオレは怖くないよ。手塚、お前から勇気をもらったからな……!」 和也の言葉に、手塚は何か胸に込み上げるものを感じた。 生まれて初めての感情だった。 ――これが……友情……なのだろうか テニスをしていた時には決して感じることはなかった想いだ。 しばらくして3人は手を振って別れたが、手塚の胸には、まだ先ほど感じた熱い想いが残っていた。 それから、和也と美佳はクラスで積極的に動いた。 最初は半信半疑だったクラスメートも、段々手塚と打ち解けてきた。 事実、手塚はぶっきらぼうな口ぶりではあるが、根は真面目だし、また他人への許容力もあった。 時折発揮するリーダーシップもクラスメートにとっては頼り甲斐のあるものだった。 3ヵ月も経った頃には、ほとんどのクラスメートは手塚を恐れていなかった。 隣の席の藤原も今では手塚をヅカちゃんと呼んでいる。 彼らは共に笑い、泣き、人並みの青春を謳歌した。 手塚にとっては、この6ヶ月間が人生で最良の時間であったかもしれない……。 七、 だが、半年を迎えた頃、事態は急変した。 元々、手塚のようなテニスプレイヤーを転校させることに、生徒の保護者からは苦情が殺到していたという。 さらに今では手塚を遠巻きに扱うのではなく、クラスメート全員が手塚と仲良く接している。 この現状は逆に極めて危機的なものと保護者たちには思われた。 クラスメートの保護者全員から学校側へ嘆願書が提出された。 これ以上、我が子をテニスプレイヤーと同じ学校には通わせられない、といった旨である。 学校側も、クラスメートも、親兄弟を必死に説得した。 しかし、保護者たちの了解は得られなかった。 保護者たちとしても、手塚という少年が心優しい者であることは理解していたつもりだったが、手塚が心の揺らぎやすい思春期の少年であることにも間違いない。 もし、手塚が一度でも感情を爆発させたなら、その時の被害は甚大なものとなるだろう。 何人何十人の死者・怪我人が出るか分かったものではない。 そして、その死者や怪我人が自分の娘・息子だったと考えるなら、保護者たちが恐れるのも無理はないだろう。 学校側は保護者の圧力に負け、とうとう手塚の放逐を約束した。 決死の任を帯びた担当がそのことを手塚に伝えたが、幸いなことに手塚は激情に任せ担当を半殺しにすることもなく、素直にその旨を受け取った。 学校側は、生徒が手塚を無用に刺激することがないよう、全校を休校とし、また手塚の放逐手続きが完了するまで、手塚への一切の接触を禁じた。 八、 「やっぱり、ここにいたんだね……」 背後から声をかけるものがいた。 満開の桜の只中、舞い散る花びらに包まれ、手塚は丘の上で夕日を見つめていた。 背後の美佳に振り返る。 「この場所は君に教えてもらった場所だったな……。もう、明日でこの街ともお別れだ。最後に、この景色を見納めておこうと思ってな」 二人の間にしばしの沈黙が流れた。 「ごめんね、手塚くん。あたしたち、ホントは手塚くんと別れたくないんだよ……。お父さんにもお母さんにも言ったんだけど、どうしても……」 美佳は涙をためている。 「いや、気にするな。仕方がない。オレがテニスをしていたという事実は、どうあっても消せないんだ」 手塚の横顔はどことなく寂しそうに見えた。 「それで……手塚くんはどうするの? 次はどこの学校に行くの?」 「実は……青春学園に戻ろうかと思っている。やっぱり、オレが普通の高校で高校生として暮らしていくのは無理のようだから……」 美佳も悲しそうな顔をする。 青春学園といえば、美佳や和也のような普通の人間が接触できる世界ではない。 青春学園に手塚が戻れば、手紙を送ることすらできなくなるだろう。 「じゃあ、これが本当に、最後のお別れなのね……」 「ああ……」 美佳の瞳から一条の涙がこぼれた。 美佳は涙を振り払い、笑顔を作って言った。 「最後に……もう一回、手塚くんのオーラが見たいな。お願いして、いいかな?」 「ああ……」 手塚は美佳の方を向き、小声で呪文を唱えた。 「我 が心すでに空なり 空なるが故に無……」 その瞬間、手塚の身体から強烈な光と風が発せられた。 キャッと美佳が目を伏せた次の瞬間、オーラに包まれ金色に輝く手塚の姿が眼前にあった。 手塚のオーラは金色の熱を発し、フシュゥゥという音を立てながら逆巻いている。 「きれい……やっぱり、手塚くんのオーラはきれいね……」 一分ほどオーラを発して、手塚の身体は本来の色を取り戻した。 「ありがとう、手塚くん……最後まで私のわがままを聞いてくれて……」 そう言って、美佳は正面から手塚に抱きついた。 人に抱いてもらったことなど、母親以外では初めてだった。 これが、人の温もりなのか――手塚は思う。 手塚も美佳の身体を抱きしめた。 つよく抱きしめたかったが、それでは美佳の身体が壊れてしまう。 手塚は初めてテニスをしていたことを後悔した。 抱き合ったまま、しばしの時間が流れた。 「ねえ、テニスプレイヤーって人の心が読めるんでしょ」 胸の中で美佳が囁く。 「いや、それはオレの後輩の能力だ。オレにはそういう能力は使えないんだ」 でも――手塚が続ける。 「いま、きみが何を考えているか。そんなことはオレにだって分かる。そして、オレも同じ気持ちだ」 くるくると桜が舞う中、二人の間に再び一瞬の沈黙が流れる。 じゃあ、当ててみて――美佳が顔を上げた。 手塚が口を開く。 「オレは、きみが好きだ」 手塚が優しく美佳に口付けし、旋風が地面を覆う桜を吹き上げた。 桜の生み出した霞の中で、二人は最後の接吻を交わした。 〈終〉 |
| 戻る |
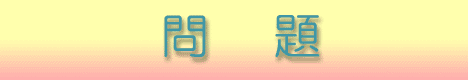
★★★完全パンクマニュアル発売中です!〈amazonで購入〉★★★