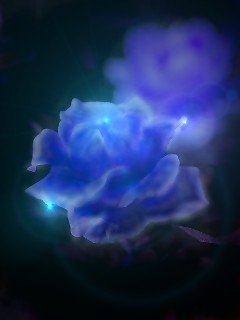
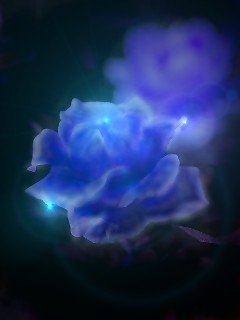
あなたの名は・・・ 第七章 イシュタル編 2
「う・・・ううん・・・・」
イシュタルは目を覚ました。
彼女の目には豪華な装飾に満ちた天井が入ってきた。
この天井には見覚えがあった。
今まで、何でも眠りから覚めたらこの天井を目には入ってきた事があった。
そう・・・ユリウスに抱かれ、眠りから目が覚めるたびに・・・
彼女は周りを見た。
見覚えのあるシャンゼリア。
見覚えのあるソファー。
見覚えのある壁にかけられた絵画。
それは、自分の知っているユリウスの部屋そのものだった。
(ここは・・・ユリウス殿下の部屋?)
彼女は自分がユリウスの部屋にいる事を知った。
それと共に湧き上がる疑問・・・
(どうして・・・私・・・ユリウス様の部屋に・・・)
彼女は自分がどうしてユリウスの部屋にいるかが分からなかった。
(確か私・・・マンフロイたちに追い詰められて・・・)
・・・チャリ・・・
「・・・えっ?」
記憶を辿っていたイシュタルは自分の手や足に違和感があるのを感じた。
彼女は自分の手を見てみる。
そこには・・・
「!?・・・な、なに?」
彼女の両手には手枷がかけられ、それは鎖によって繋がれていた。
彼女は自分の全身を首を上げて見つめた。
「・・・こんな・・・」
彼女は自分の姿に愕然とした。
彼女は全裸でベットに横にされていた。
そして、彼女の四肢には枷がつけられており、それは鎖でベットの四隅にある柱につながれていた、
手は万歳の体勢をとらされ、足は限界まで広げられていた。
彼女はいま、ベットの上で大の字の状態で拘束されていたのだ。
彼女は手足を動かしてみたが、まったく動かすことは出来なかった。
「一体・・・これは!?」
彼女は混乱した。
なぜ、自分がこんな恥ずかしい姿で拘束されているのか・・・
なぜ、ユリウスの部屋でこの様な状態いるのか・・・
その時、この部屋の入り口である扉が開き、一人の青年が入室してきた。
「イシュタル・・目が覚めたか?」
それは赤い髪を靡かせた青年、ユリウスだった。
「ユリウス様!?」
彼女は驚いた声を上げた。
自分が裏切った青年が・・・自分の初恋の相手の変わり果てた姿をもつ青年が・・・
彼女の前に現れたからだ。
「目醒めはどうだい?イシュタル・・・」
ユリウスはゆっくりとイシュタルに近づいてくる。
そして、彼女の寝かされているベットの脇まで来た。
「イシュタルがあまりに目覚めなかったから心配したぞ。」
「ユリウス様・・・私は一体なぜここに・・・」
彼女は恐る恐るユリウスに質問をした。
「記憶はないのか? 私がお前に口づけをした記憶が・・・?」
その記憶はあった。
ユリウスが自分にキスをした記憶は・・・
その後、意識が遠のいていったのだ。
「あの後、お前を連れ帰ったのだ。安心しろ。傷や体を蝕んでいた毒は回復魔法で完治させたから・・・」
ユリウスはイシュタルの顔を覗き込む。
その顔に生気が戻っていることにユリウスは満足しているみたいだった。
「それにしてもどうだい?今の自分の姿は・・・恥ずかしいかい?」
ユリウスは悪魔的な笑顔でイシュタルに尋ねてきた。
「あ、当たり前です! なんで・・・こんな格好をさせるのですか?」
彼女は顔を赤らめている。
その姿にユリウスはさらに顔を歪めた。
(私を陵辱した時の・・・ユリウス様の顔だ・・・)
その顔にかつて自分の純潔を奪った時の表情が、今のユリウスに重なった。
記憶を失う直前に見た、昔のユリウスの顔ではなかった。
「言っただろう?私はお前の事を愛していると・・・」
「・・・・・・」
そのことのイシュタルは覚えていた。
そう言ってから、ユリウスはイシュタルにキスをしたのだ。
「お前が私から離れていった・・・帰りたくないと言った・・・お前は私と共に歩む道を否定したのだ。」
「・・・・・・」
「しかし、私はお前を離したくはない。お前の事を愛しているからな・・・だから、・・・」
彼は腕を伸ばして、イシュタルの胸を鷲掴みにした。
「ううっ!」
「お前を・・・変えてやる。 私なしでは生きられない体に・・・」
ユリウスもベットの上に乗ってきた。
そして、イシュタルの上に覆い被さってきた。
「ユリウス様!! やめてください!私を変えるって・・・」
「お前の体に私が与えてくる快感、悦楽をしっかりと染み込ませてやるんだ。たとえお前の心はどうであれ、体は私から離れられないようにしてやる」
「そ・・・そんな! そんな事をして何になるというのですか?」
「お前を離したくないんだ。」
彼の口調が強くなっていく。
「お前はあの女、ティニーを助けるために私を裏切った、しかし、それだけではなかったはずだ。私の残虐な行為、性格を見て私から離れたいと思っていたのだろう?」
「ユリウス・・・様?」
「離れさせはしない。お前は私のものだ! もう、私から離れようとは思わないようにしてやる。」
彼は両手で彼女の双丘を激しく揉みまわした。
「いや!やめて、ユリウス様!!」
彼女は体をくねらせながら、ユリウスに抗議する。
「ふふっ・・・イシュタルはここを激しく責められるのが相変わらず弱いな・・・」
ユリウスはイシュタルとの今までの情交を思い出しながら笑った。
彼は、イシュタルが胸を痛いほど揉まれるのが非常に弱かったのを知っていたからだ。
「あ・・・うっ・・」
彼女の口から弱点を責められて、感じてしまう声が醸し出されてくる。
「お前の声はいつも可愛いな・・・普通に会話をするときは透き通るような美しい声なのに・・・こんな風に感じている時は甘く切ない少女のような声に変わるのだな。」
ユリウスはさらにイシュタルの胸を責めた。
強く揉み、時には優しくマッサージをするように彼女の胸を撫で回した。
「はっ・・・くっ・・・ふふん・・・」
彼女はたちまちユリウスの手の動きに支配されていってしまう。
今まで何度もイシュタルを抱いてきたユリウスにとって、彼女を感じさせることなど造作もないことだった。
「では・・・始めるとするか・・・」
彼は自分のポケットから一つの小さな瓶を取り出した。
ガラスと蓋によって閉ざされたその中には透明なクリーム状の液体が入っている。
「これは媚薬の一種で『ロプトフラワー』という薬だ。複数の媚薬を魔法で調合された薬でね。これを塗れば感度が高まり、飲めば体を燃え盛るように熱くさせることができる薬なんだ。これを使ってあげるよ・・・」
イシュタルは凍りついた。
ユリウスは薬を使って自分を辱めようとしている。
(いやだ・・・そんなのいや!)
「やめて!ユリウス様! そんな薬使わないで!!」
イシュタルは体を暴れさせたが、拘束されているために無駄な行動だった。
「ふふふっ・・・怖がることはない・・・さあ、まずはここに・・・」
ユリウスは蓋を開け、中指と人差し指で中のクリーム状の液体をすくい出すと、それをイシュタルの乳首に塗りこんだ。
左側から・・・次に右側に・・・
「ひゃん!」
塗られた瞬間、凍りつくような刺激が彼女に走った。
何か、氷でも当てられたような冷たさが乳首を締め上げる。
(凍ったように冷たい感覚・・・これは一体・・・)
その冷たさにイシュタルは戸惑った。
乳首はその冷たさに反応したのか、これ以上ないほど勃起する。
「ふふっ、冷たいだろう・・・この薬を塗られると最初に感度を高める作用があるんだ。いま、君が感じている冷たさは、感度を上げる過程で感じる一種の副作用みたいなものでね。しかし・・・時間が経つと・・・」
「あ・・・ああ!!」
これ以上ないほど冷たくなっていたのが、次の瞬間、燃えるように熱くなっていった。
「焼けるように熱くなって、君の体を狂わせるんだ。もちろん高まった感度のままね。この薬を使えばどんな聖女もその効能に淫女に変わってしまうそうだ。」
彼は一旦薬をしまうと、隆起した乳首に手を当てた。
触れただけで、彼女の体がビクン!と震える。
「なるほど・・・ここまで感じやすくなるとはね・・」
「あ、熱い! ユリウスさまああぁ!・・・さ、触らないでえぇっ!」
イシュタルは乳首がこれ以上ないほど熱くなり、ユリウスの鼻息さえも敏感に反応してしまう。
そんな状態の乳首をユリウスはつねったり、摘み上げたりして嬲っているのだ。
あまりの刺激にイシュタルは意識が遠のきそうになってしまう。
「うああぁぁぁっ!・・・はっ・・・や、やはああうぅ・・・」
大声を上げて、嬌声をあげてしまうイシュタル。
まるで、自分のその部分だけ別世界にあるような感覚をもってしまう。
「凄い効き目だな。よし、他のところにも・・・」
ユリウスは再び瓶を取り出すと、それの蓋を開けた。
ユリウスは次に下半身に自分の身を持って行って、イシュタルの開かれた股間に見つめた。
そこは既に胸を嬲られた際の刺激によって、下のシーツを湿らすほど濡らしていた。
「イシュタルのここ、ベチョベチョに濡れているじゃないか。穴が開いてたっぷりと蜜を出しているよ。」
「いや・・・いや! 言わないで・・・ユリウス様・・・」
「顔が赤くなっているな。恥ずかしさと快感の狭間で揺れるイシュタル顔を限りなく、いやらしくて可愛いよ・・・」
ユリウスはそう言いながら再び薬を指ですくうと、その右手を彼女の秘所に近づける。
「さて・・・イシュタルの豆にこれを塗ったらどうなるのかな・・・」
ユリウスは左手で彼女のクリトリスを摘み出しその包皮の中から実を取り出すと、薬をすくった手を近づけていった。
「そんな薬・・・やめて、お願い! 塗らないでください!!」
ユリウスはイシュタルの願いを無視して、薬を塗りこんだ。
クリトリスを薬を含んだ人差し指と中指に挟んですり込ませる。
「ひゃああああぁぁっ!」
彼女の敏感なところに、冷気のような冷たさが当てられる。
そして感度が上がったあとにくる脳髄に突き刺さるような熱さという名の刺激。
「あ・・・あつ・・・い・・・ふぁははあああぁぁ!」
クリトリスに媚薬を塗られたイシュタルは、あまりの快感に背筋を仰け反らせ甲高い声をあげる。
ユリウスが、フーっと息を吹きかけると・・・
「はああああん!あっ!はああぁぁ!!」
彼女は体が息を吹きかけるたびに弾む。
ただの空気の流れさえ、今の彼女には自分の性感を刺激する愛撫になっている。
「息だけでこれでは・・・触ってみたらどうなるのかな・・・」
ユリウスはクリトリスを指で転がしてみた。
彼女の体が激しく揺れ、その下にある秘裂からは蜜が止めどなく流れ出した。
「なるほど、たったこれだけを塗っただけでこれとは・・・ふふっ、これなら確かに禁欲を旨とするブラギの巫女でさえ簡単に堕せそうだ。」
ユリウスはそう言いながら、イシュタルのクリトリスを摘み上げた。
「あ!?・・・いややああああぁぁぁぁっ!」
ビクン!!
ブシュ―――・・・
彼女の体が激しく弾んだ。
鎖の拘束がなければ飛んで行ってしまえるかと思うくらい・・・
と、同時に彼女の秘所から愛液が激しく飛び散った。
その様子をユリウスは目を細くしながら見ていた。
「・・・まさかイシュタル・・・もうイッタのか?」
彼女は答えず、目を閉じてただ荒い息遣いをしているだけだった。
彼女の瞼の間からは一筋の雫が落ちていった。
「はっはっはっ!・・・まさかこれだけで絶頂まで昇るとは・・・この薬の力も大したものだが・・・イシュタル、お前も随分と淫乱なのだな?・・・これだけでイッテしまうとは・・・」
「う・・・うっ!・・・うわあああああぁぁ!」
彼女は声を上げて泣き始めた。
彼女は恥ずかしかった。
薬のためとは言え、これだけの痴態をユリウスに晒して・・・
抵抗したくても、鎖と快感のためになにもできない自分が嫌だった。
「さてさて・・・イシュタル、次はどこを気持ち良くしてもらいたい?アソコか?それとも脇の下にでも塗ってあげようか?くすぐった時にどれほど笑い転げるかが楽しみだ。」
くすくすと笑いながら、ユリウスはその光景を頭の中に思い描いているようだ。
「もう・・・やめてください・・私・・・こんな薬で責められ続けたら・・・」
イシュタルは絶頂の余韻が引かない状態だったため、その声はひどく小さく弱いものだった。
「責められ続けたら・・・?」
「・・・こ、壊れてしまいます・・・」
イシュタルはこんな責めが続いたら、自分が快感と恥辱によって壊れてしまう恐怖に駆られた。
「だったら、壊れてしまえ・・・私の肉奴隷となって生きてみるか?」
ユリウスは再び薬をすくうと、再び股間に近づけていった。
「やめてユリウス様!これ以上・・・アソコになんて塗らないで!!」
「アソコではない・・・」
彼の手はイシュタルのヴァギナを通り過ぎて、彼女のアヌスへと向かって行った。
「そ、そこは!?」
「お前はここを使うことは前々から嫌がっていたからな。この際だ。ここをたっぷりと楽しめるようにしてやろう・・・」
ユリウスは問答無用に彼女のアナルに媚薬付の指をねじ込んだ。
「くうううぅぅぅぅっ!」
彼女はアナルに指が侵入にしてくる感触に悲鳴をあげる。
「あまりここは使わなかったからな・・・かなり狭いな。まあ、この指をくわえ込んで離さないような狭さもまた良いが・・・」
決してイシュタルはアナル処女ということではなかったが、それでも今までの情交であまりユリウスにこの場所を使わせなかったことも事実だった。
トロリとした媚薬がローション代わりになって指の挿入の手助けをする。
そして腸壁に付着した媚薬が彼女のアナルを性感が感じられる場所へと変える。
「痛っ!・・・あああぁ!」
慣らされていないまま挿入された痛みと、媚薬の与えてくる快感に二種類の声を上げる。
イシュタルに指を挿入したユリウスは、指を掻き混ぜるように動かす。
突き入れるだけではなく、中で指を折り曲げて解していくような動きもした。
「う!・・うっ、ああん・・・くはああぁぁっ!」
いつもなら苦痛と痒さに満ちたこの責めも、今は媚薬のせいで甘く、激しい性感となって彼女を狂わせる。
「どうだ?アナルを使って感じるのは? 結構良いものではないか?」
「はあ!はあっ!・・・きもちよく・・・なんて・・・」
「指を咥え込み、腰を淫らに振りながらよく言う・・・かなり感じているみたいじゃないか?ここを使われるのを嫌っていたお前がこの場所で悶える姿は本当に愉快だな。」
彼は右手でアナルを責める傍ら、左手を再び敏感になったままの乳首に当てられた。
アナルと乳首の二箇所を責めたくるユリウス。
その責めにイシュタルの秘所は、まるで自分も責めてくれと言わんばかりに愛液を滴らせる。
しかし、イシュタルの体が一番責めを望んでいる場所をユリウスは責めなかった。
彼女自身の心はいざ知らず、ユリウスはそう簡単にイシュタルを満足させるつもりはなかった。
代わりに胸とアナルを指で蹂躙した。
その感覚にイシュタルは嬌声を上げる。
特にアナルはイシュタルの気持ちは無視し、ユリウスの指を締め付け自分から快楽を貪ろうとしていた。
媚薬によってアナルは、イシュタルの性感帯として開発されていく。
「く、くううぅぅっ!あ、あああああうううぅぅぅぅっ・・・!!」
再び彼女の体が仰け反り、彼女は絶頂を迎えた。
彼女はとうとうアナルを犯されて、昇り詰めてしまった・・・
その様子を見つめていたユリウスは心底愉快だった。
「どうだ!?アナルも気持ち良いものだろう・・・媚薬を使い、胸を同時に責めていたとは言え、指だけでイクことができたんだ。お前のここは相当な素質を持っているみたいだな。」
アナルに今だ埋め込まれた指を震わせながらユリウスは喋った。
ユリウスの言葉をイシュタルは否定できなかった。
実際、尻の穴で絶頂を迎えてしまったのだ。
何を言うことができるというのか・・・
「ふふっ、これでイシュタルはここでも感じられるようになったんだ・・・ここは一つ・・・」
ユリウスは手を伸ばし、ベットの横にある棚からあるものを取り出した。
それは男の男根に模した黒い張り型だった。
普通の男性よりかなり大きいものであり、その表面にはぶつぶつしたイボが無数にあった。
それを見たとき、イシュタルは背筋が凍りつくような感覚を覚えた。
「ユリウス様!それは・・・」
ユリウスは笑みを浮かべながら答えた。
「張り型だよ。これをアナルに突き入れてあげるよ。せっかく感じるようになったんだ。これを入れてあげよう・・・」
「やめて・・・お願いそんなもの入れないでください!お願いです!」
「今までだって、私のモノを受け入れたことはあっただろう。これぐらい大丈夫だ。」
そう言って、ユリウスはイシュタルの菊に張り型を挿入していった。
ズズ・・・ズズズッ!
「はぐう!」
彼女のアナルに黒い張り型が埋め込まれていく・・・
あまりに大きな張り型の挿入にイシュタルの呼吸が一瞬止まる。
「飲み込んでいく・・・イシュタルのアナルがこの太いものを飲み込んでいくよ・・・」
「やめて・・・言わないで!ぅぐっ!!」
確かに媚薬の効能で感度は上がっていた。
その快感を上回る圧迫感がイシュタルにかかった。
僅かに苦しそうな声を上げるイシュタル。
しかし、ユリウスは構わず突き入れ続ける。
そして抵抗を抑え込み、彼女の中にその全身が埋まる張り型。
「きつい・・・いたい・・・」
「全部咥えたんだね。くくっ・・・肛門が限界まで開いているよ。でもよくこれだけ大きなモノを咥えることができたね。本当に動くかな?」
ユリウスは張り型を動かし抽出を開始した。
「ひいいぃぃ!・・・う、動かさないで・・・さけちゃう・・・裂けてしまう!」
「さすがにこれじゃ・・・まともには動かないか・・・」
ユリウスは力任せに張り型を動かしてみたが、限界まで広げた状態のアナルではこれ以上動くための余地は残していなかった。
「動かせないのでは仕方がないな・・・それじゃ・・・」
ユリウスはイシュタルの顔を覗き込んで話し掛けた。
「イシュタル・・・もしこの張り型の中に大量のロプトフラワーが詰まっていて、ボタンを押したら、それが流れ出すと言ったらどうする?」
苦しさにまみれていたイシュタルはユリウスの言葉を瞬時に理解できなかった。
「えっ・・・いま・・・なんて・・・」
彼の言う事を聞いていなかったイシュタルにユリウスは・・・
「つまり・・・こういうことだよ。」
次の瞬間、彼女に思い知らせた。
彼は張り型の根底部にあったスイッチを捻り
それと同時に、張り型のイボイボから大量の媚薬が流れ出した。
今までにない大量の媚薬をアナルに直接注入されたイシュタル。
「うわああああぁぁぁぁっ!!」
彼女は絶叫を上げた。
冷たさと熱さ・・・快感と苦痛が彼女にどっと押し寄せてきたからだ。
「この中には私の持っている瓶と同じぐらいのロプトフラワーが入っていたからな。どうだい?これだけの量の媚薬がアナルの中に放たれた気分は・・・?」
「くううわあああああああああぁぁぁぁぁ!!」
ユリウスはイシュタルに訊ねたが、その時には彼女の体が激しく痙攣をした。
大量の媚薬によって一気に限界まで昇らされたのだった。
その後、彼女の体が数秒間、痙攣をした後・・・彼女の体は力を失ったように崩れた。
あまりの度重なる絶頂、そして媚薬の強すぎる刺激に悶絶してしまったのだ。
「イシュタル・・・またイッタのか?」
彼女は体をヒクつかせながら・・・気絶していた。
「なんだ・・・気を失ったのか・・・」
「どこだよ!イシュタル〜!」
ユリウス様が私を探して走り回っている。
そんなユリウス様の一生懸命な姿がたまらなく愉快で、微笑ましくて・・・
「あははっ! ユリウス様、ここですよ〜!」
私は木の幹の上から手を振ってユリウス様に呼びかけた。
この広い庭園のこの大きな欅の木に私は登っていたのだ。
私を見つけたユリウス様が大声を上げた。
「そこにいたのか・・・って、そんな高いところにいたら危ないよ!」
クスクスと私は笑って・・・
「大丈夫ですよ! 私はトラキアでこれより高い木にも登ったりしているのですから・・・」
私はそう言いながら、ユリウス様の元に行くためにこの木を降り始めた。
その時・・・
「あっ、キャ――――!」
私は足を滑らしてしまった。木から落下してしまう。
「イシュタル!」
ドシン!
「あっ・・・」
ユリウス様は私を助けてくださった。
私が落下するところに滑り込み
ユリウス様は落ちてきた私の体をしっかりと抱えてくれたのだ。
でも、落下で勢いのついていた体を完全には抱きとめられず、ユリウス様は私を抱えたまま尻餅をつかれてしまった。
「いてて・・・イシュタル・・・大丈夫?」
私は飛び起き・・・
「すいません! ごめんなさい! 大丈夫ですか、ユリウス様!?」
顔を赤くしてユリウス様を見つめる。
ユリウス様が怪我をしていないか心配だったし、木から落ちてしまった自分の事が何より恥ずかしかった。
「大丈夫、大丈夫・・・」
「本当に大丈夫ですか?怪我などは・・・」
「僕は大丈夫だよ。それよりイシュタルは大丈夫?怪我はなかった?」
ユリウスも立ち上がって、服をパンパンはたいた。
「私は大丈夫です・・・だって、ユリウス様が助けてくださいましたから・・・」
「よかった〜イシュタルが怪我をしなくて・・・」
「ごめんさい・・・私、重たかったですよね・・・」
「そんなことはないよ。イシュタルは軽いよ。まるで妖精のようにフワフワしていたよ!」
「言いすぎですよ!?そんなに軽くなんてないです!」
「あはは・・・でも、イシュタルに怪我がなくて本当によかった・・・」
ユリウス様はいつもの笑顔を私に向けてくださった。
「イシュタルに
(この方は・・・本当にお優しいんだ・・・)
いつも私には優しい笑顔を見せてくださる。
いつも私を気遣ってくださる。
今も、私を守ってくだされた。
私は、そんなユリウス様の優しさが・・・優しい顔が私は好きだった。
なのに・・・どうして・・・
ユリウス様・・・あなたは変わってしまわれたのですか!?
ギュ!
「ああああぁぁぁぁっ!」
体を凄まじい刺激が走った。
自分の乳首が何者かに捻られたせいだった。
敏感になった乳首からは異常な快感が発せられた。
イシュタルはその激しい刺激で目を覚ました。
「イシュタル、目覚めたか?」
目覚めたイシュタルをユリウスは覗いていた。
イシュタルはすぐに自分の状況を確認した。
自分の置かれた環境はまったく変わっていなかった。
手足の拘束も彼女の体を追い詰めた媚薬も、そして彼女の菊の部分に埋め込まれた張り型もそのままだった。
彼女は自分があの極限状態から気絶をしてしまった事を知った。
「お前イッテ、気を失ったんだ。まあ、時間にして数秒ぐらいだったが・・・」
数秒間というのは間違いではないだろう。
実際、彼女は目覚めてからすぐに体中に、媚薬から与えられてくる性感の波を感じたのだから。
「ふふっ、アナルの味はどうだった?美味しかっただろう?」
「ユリウス様・・・」
「さて・・・次はどこを責めてほしい?アナルの次はやはりヴァギナか?お前のここは既に与えられる快感によって溢れ出すように濡れているからな・・・」
ユリウスはそう言いながら、彼女の花びらを指で弄くる。
「あひっ!」
「ふふっ、ここは媚薬を塗らずとも十分すぎるほど感じやすくなっているみたいだな。襞が熱い汁を含んでビクビクしているぞ。」
クチャクチャと指を動かして彼女の中を掻き回していく。
「う・・・ふ・・動いている・・私の中でユリウス様の指が・・・」
ユリウスは指を動かすたびに彼女の愛液が溢れ出してくる。
それが張り型によって塞がれているアナルを通り過ぎ、ベットのシーツを濡らしていった。
「こんなに流して・・・本当にイシュタルは厭らしいのだな。」
ユリウスはそう言いながら、指の動きを速めていく・・・
「う、くわあぁぁ!・・・やめて・・・おかしくなる。」
散々、胸やクリトリス、アナルを責められていたのだ。
イシュタルのアソコはこれ以上ないほど感じやすくなっていた。
イシュタルを嬲りながら、段々とユリウスの顔が醜く歪んでくる。
「さあ、腰を振れ!もっと快楽に身を委ねよ。いくらでも快楽を貪るが良い。そうすればお前は私から離れられなくなる。身も心も私のものになるんだ!」
その時、イシュタルの中に何かが走った。
「・・・・・・」(この方は・・・)
ユリウスに嬲られながら、イシュタルは・・・
「どうして・・・」(どうして私・・・私を・・・)
イシュタルの冷静で透き通った声にユリウスは思わず責めを中断してイシュタルを見つめた。
「イシュタル?」
イシュタルの体がふるふると震えている。
しかし、それは快感に悦びをあげている訳でも、苦痛に打ち震えているわけでもなかった。
ただ、彼女は悲しかったのだ。
「どうして・・・どうしてですか!?ユリウス様!!」
「ど、どうしたんだ・・・」
イシュタルの鋭く悲痛に満ちた声にユリウスは動揺した。
「なぜ、私を体で繋ぎ止めようとするのですか?なぜ、私の心を無視して自分に従わせようとするのですか!?」
イシュタルは渾身の力で叫んだ。
「私はユリウス様の事が好きでした。愛していました。そう・・・あの幼き時にあなたと出会って、あなたの優しさや笑顔に惹かれて・・・大好きになりました。そして、ユリウス様は必ず迎えに来てくれると言ってくれました。本当に嬉しかった・・・でも」
イシュタルの脳裏に、再会した後のこと事が浮かび上がっていく。
「あなたは変わってしまいました。優しい心も笑顔も消えて・・・ただ、暗黒神の化身としてのユリウス様となって再び私の前に現れました。そして、力と恐怖によって私を支配したのです・・・」
「・・・・・・」
「そして、今も私を支配しようとしています。どうして、なんでなのですか!?私はあなたの事が好きだったのに・・・どうして、私のその心を無視するような方法で私を支配しようとするのですか?私は・・・大好きだった昔のユリウス様のように微笑んで欲しかっただけなのに・・・ただ、優しい笑顔を見たいだけなのに・・・」
彼女はこの数年間の想いを全て吐き出していた。
今まで言えなかった・・・ユリウスに言うことができなかった、自分の悲しみ・・・
「ユリウス様が昔のように優しく微笑んでくだされば、それだけで良かったのに。私の愛したユリウス様なら、きっとそうしてくださるのに・・・あなたはただ、欲望に従って私を犯しているだけなのです。」
ユリウスは震えていた。
怒りからではない。
「やめてくれ・・・イシュタル・・・」
「あなたは一体誰なのですか!?あなたは私の愛したユリウス様ではない!今のあなたはただ、狂気に満ちた存在です。あなたがあの優しいユリウス様を奪ってしまったのですか? 返して・・・私のユリウス様を返してえぇっ!!」
大粒の涙を流しながら、イシュタルは絶叫した。
彼女はやっと、自分の想いを伝えられた。
彼に言いたくても言えなかった自分の気持ち・・・
イシュタルはユリウスの優しい笑顔を欲していただけなのだ。
彼に付き従っている間も・・彼女はいつかユリウスが優しい笑顔を見せてくれると信じていた。
しかし・・・ユリウスは・・・
「お願いだ!黙ってくれイシュタル!!」
ユリウスも声を張り上げた。
そのあまりの声にイシュタルは驚いた。
声の大きさもそうだが、あまりに感情を顕わにしたユリウスの声に・・・である。
「ユリウス・・・様?」
「お前に何が分かる! 僕の気持ちを・・・僕がどんなに苦しんだのか!?」
(僕?)
ユリウスの一人称が変わった事をイシュタルは聞き逃さなかった。
「イシュタルは知らないだろうな・・・僕がどうしてロプトウスに目覚めたのかを・・・どうしてこんなに狂気に満ちた男になったかを・・・」
「ユリウス様が・・・ロプトウスに・・・」
イシュタルはユリウスの言葉に呆然とした。
たしかに、イシュタルはユリウスがどうしてロプトウスに目覚めたのかを知らなかった。
彼女なりに、あのマンフロイが何かをしたのだと推測していたが・・・
「知らないだろうなイシュタルは・・・ふふっ、僕が自ら望んでロプトウスになったことなんて・・・」
自嘲気味な乾いた笑いをしながら、ユリウスは告白した。
自らの意思でロプトウスになった事を・・・
その言葉を聞いて、イシュタルに衝撃が走った。
「そ、そんな・・・嘘よ! あの優しいユリウス様が自ら望んでロプトウスになるわけがないわ。」
イシュタルは信じられない。
あの優しい笑顔を持った少年が暗黒神になる事を望むなど考えられなかった。
「本当だよ。僕は自ら望んでロプトウスになったんだ。」
「嘘です!嘘ですっ!」
イシュタルは首をブンブンふるって否定する。
自分の知っているユリウスなら、そんなことはしないという確信があったからだ。
「だったら・・・見てみるか?僕がどのようにしてロプトウスになったのかを・・・」
そう言うとユリウスは自らの右手をイシュタルの額に当てた。
「ユリウス様?」
「僕の記憶を・・・送ってあげよう。」
ユリウスは手に魔力を集め、それをイシュタルに向かって注入をし始めた。
魔法で彼女の脳に、直接自らの記憶を送ったのだ。
「えっ・・・あっ・・・」
イシュタルは頭の中が真っ白になっていくのを感じた。
そして、白い空間が突如、暗闇に変わってイシュタルはその中へと落ちていった。
そしてイシュタルは過去のにあった出来事を知る・・・