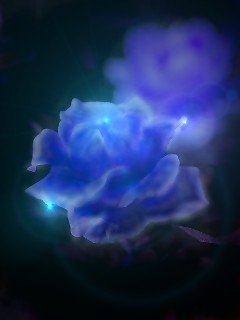
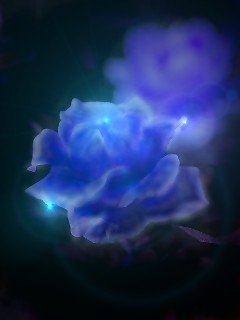
あなたの名は・・・ 第九章
昼にバーハラ城で起きた虐殺によって、民衆だけではなく帝国軍諸隊にも恐怖を与え、帝国軍の兵士たちはサポタージュを開始しその戦力は事実上無力化した。
バーハラの守備戦力が瓦解しつつあり、残ったのは十二魔将の手勢と近衛騎士団のヴァイスリッターしか存在していなかった。
これだけの戦力では解放軍の進行を食い止められるはずがなく、既に帝国の崩壊は時間の問題と思われた。
だが、帝国軍としてはこのまま手をこまねいている訳にもいかず、解放軍に対して逆撃をかける事が決定した。
フリージ城まで進出してきた解放軍に対して先制攻撃を仕掛けるのである。
その役目を行う事ができるのは、今となってはヴァイスリッターと12魔将の軍のどちらかしかなかった。
そして、その役目はヴァイスリッターに任されることになる。
本当は近衛騎士団が帝都を離れることなどまずありえない事なのだが、既に実態はロプト帝国となっていたグランベル帝国ではヴァイスリッターよりロプト自慢の十二魔将の軍の方が重要な位置にあった。
そのため勝てるかどうかも分からない攻撃に不要なヴァイスリッターが動員されることになったのである。
ヴァイスリッターの出撃は明朝に行われることになり、その旨は全軍に伝えられた。
一方、解放軍はフリージ城を制圧した後、すぐにバーハラ進撃の準備を始めていた。
連戦において解放軍は疲弊と消耗の極みにあったが、それでも一刻も早く帝国を打倒し、この大陸に平和を取り戻すという目的のために戦いを一刻も早く終わらせようとしていた。
そして、ついに明朝、解放軍はバーハラに進撃することになった。
結果的に両軍の出撃は同時に行われることになった。
その日の夕方・・・
解放軍の出撃を明朝に控えたフリージ城の一角では、一つの騒ぎが起きていた。
「こら!待ちなさいって!」
「きゃははっ!お姉ちゃん!こっちにおいで〜」
「ほらほら、静かに寝てくれよ・・・」
「いやだもん!もっとお兄ちゃんと遊ぶんだから!」
妙な喧騒がフリージ城の宿舎の前の広場で繰り広げられていた。
解放軍の若手の戦士たちが子供たちと追いかけっこやらなにやらを繰り広げていた。
夕方にもなり子供たちも休む時間だったが、どうやら遊んでいる子供たちはエネルギーが有り余っているみたいであった。
なぜ、戦時下の城で子供達が解放軍の戦士と遊んでいるかというと理由があった。
実は解放軍がフリージ城を制圧した翌日、フリージ城下の修道院から多くの子供達が保護されたのだった。
実はこの子達は各地の子供狩りによって集められた子供たちであった。
バーハラに集められていたはずの子供たちの一部がフリージの修道院によって保護されていたのだ。
子供たちを秘密裏に保護していたのは、グランベル皇帝アルヴィスの側近であったフェリペという者だった。
彼は皇帝の密命を受けバーハラに送られる途中に通過するフリージで子供たちを匿い、今まで保護していたというのだ。
そして先日、解放軍が城を制圧し安全が確認されたのを見計らったフェリペは解放軍に子供たちの身柄を預けたのだった。
子供たちを預かった解放軍は後方の安全地帯に子供たちを移動させる事にした。
子供たちの移送は明日行われることになったのだが、それまでは子供たちの相手が必要だった。
そのため解放軍の若手の者達が子供たちを移送するまでの間、面倒を見ることになったのだった。
「もう、疲れた・・・」
「こら、レスター!なにへばっているのよ!」
大の字で倒れこんだレスターをパティは叱咤する。
周りではレスターと同じように倒れ込む者が続出していた。
解放軍の歴戦の戦士たちが幼き子供たちの前に息切れしていた。
子供たちは長い時間を道院の狭い一室で狭苦しい思いをさせられながら帝国の追及の目から逃れていたのだ。
そして今、子供たちは解放された。
溜まっていた鬱憤とエネルギーを放出するかのように遊び始めたのだった。
その圧倒的なエネルギーの直撃を受け、解放軍の者達は次々と脱落していった。
木に上ったり、追いかけっこをさせられたり、かくれんぼを半日以上続けていれば当然だろう。
今の時点で子供たちと対等に渡り合っているのはトラキアで孤児院を営んでいたファバル・パティ兄妹やフィー、ラクチェぐらいなものであった。
他の者達は座り込んだり、息を切らしていた。
明日は戦いが控えているのに、本当に良いのだろうか?
「ふぅ・・・」
ティニーは広場の脇にある木に寄りかかり、座った。
彼女もついさっきまで子供たちと遊んでいたが、さすがに体力の限界に達し、ひとまず休憩をすることにした。
彼女は子供達が好きであり彼らと童心に帰って遊ぶ事が楽しかった。
無論、さすがに子供たちと同じように体力が尽きるまで遊び続けるということはできなかったが・・・
「ティニー・・・隣、いいかな?」
木の下で休んでいたティニーの傍にセティが近づいてきた。
彼も息を切らして休もうとしていたみたいだった。
「あ、もちろんですよ!セティ様!」
彼女はただでさえ顔が赤かったのにセティが来た途端、さらに顔を赤くして彼に席を提供した。
二人は共に座って、子供たちの暴れる様を見つめていた。
「子供たち・・・凄く元気ですね」
「ああ、とっても元気だ。あまりに元気すぎて、こっちが参ってしまいそうだよ・・・」
「うふっ・・・そうですね・・・」
二人とも優しい視線で子供たちの元気な姿を見つめていた。
「そう言えば・・・知っている?」
しばら休んで息を整えた後、セティは喋り始めた。
「・・・なんですか?」
ティニーはセティの顔を覗き込んで、彼に視線を向けた。
「私は変だと思っていた事があったんだ。あの子供達が匿われていた修道院が帝国の追及から逃れられたことなんだけど・・・」
「あ、私も不思議に思いました。子供狩りにおいて各地から集められた子供たちと、バーハラに着いた子供たちの数が違えば、必ず帝国は捜索を行うはずです。その捜索の中で、フリージも徹底的な捜査の対象になったはずです。それを逃れられたなんて・・・」
「実はそのことなんだけど・・・」
セティは一旦言葉を切った後、真剣な顔になって続きを述べ始めた。
「どうやら、イシュタル殿があらかじめ、この修道院は自分が懇意にしている場所だから、捜査のために手を入れて汚すなという、一種の脅しを捜索部門にしていたみたいなんだ。」
「えっ?・・・イシュタルお姉様が・・・?」
(知らなかった・・・)
イシュタルが、そのような行動を取っていたことをティニーは知らなかった。
「もう、随分前にイシュタル殿はその行動をしたみたいなんだ。おかげで、兵士たちはイシュタル殿を恐れ、修道院には手が出せなかったらしい・・・」
「そう・・・なんですか・・・」
ティニーは改めてイシュタルの優しさを感じた。
イシュタルは自分の出来得る範囲で子供たちを精一杯助けていたのだ。
露見すれば自分のみが危うくなるであろうが、それでも彼女は子供達を救うべく尽力していたのだ。
「今、イシュタルお姉様はどこにいらっしゃるのかしら・・・」
「分からない・・・捕虜にした帝国兵も彼女のことは知らないみたいだった。今、イシュタル殿はどこに居るのか・・・?」
イシュタルの行方はユリウスを始めとする極少数の者しか知らなかった。
それ以外の人々にはイシュタルは行方不明という情報はなかった。
「イシュタルお姉様に・・・もう一度会いたい・・・」
「ティニー・・・」
途端にティニーの胸の内に熱い感情が込み上げてきた。
自分を幼い頃より優しく愛してくれた自分にとって家族といえる女性であり、先日、自分の危機を命懸けで守ってくれたイシュタルに思いを馳せる。
自分にとって大切な彼女が依然として消息不明であり、もう、会えない可能性すらあるのだ。
ティニーにとってイシュタルとはもう会えないことなど、とても受容できるものではなかった。
まだ、彼女と別れて数日しか経っていない筈であったが、もう、何年も会っていないような感覚に襲われる。
その感覚が彼女の瞳から涙を溢れさせていた。
「会いたい・・・会いたい・・・です」
うわ言のように願いを述べるティニーをセティは見つめ、いかに彼女がイシュタルの事を大切に思っているかを知った。
「ティニー・・・信じよう・・・」
セティは彼女を励まそうと思い、彼女の手を取った。
「セティ様・・・」
「必ず会える・・・もう一度、イシュタル殿と会いたいと願っていれば、必ず会えるよ。だって、ティニーはこれだけイシュタル殿の事を大切に思っているんだ。きっと、神様は君の気持ちを分かってくださり、君の願いを叶えてくれるはずだよ。」
ぎゅっとセティはティニーの手を強く握った。
「だから、希望を捨てずに行こう・・・きっと、イシュタル殿に会える事を信じて・・・」
「セティ様・・・」
ティニーにはセティが自分を優しく励ましてくれている事が分かった。
落ち込んでいる自分を助けてくれようとしている彼の事が・・・
それだけ自分を愛してくれる彼の存在がティニーには嬉しかった。
そして、そんな彼のことをセティは愛しく思っていた。
「はい・・・私、いつまでも信じます。イシュタルお姉様に会える日を・・・」
だから、彼女はいつまでも信じることにした。
愛しい彼が自分を励まそうとしてくれた事を・・・
そして、大切なイシュタルに会える日が来る事を・・・
「お兄ちゃんにお姉ちゃん!何してるの?遊ぼうよ!」
一人の少年が二人の近くに寄ってきた。
休んでいる彼らを遊びに連れ出すためであろう。
「あ、分かったよ。ティニー!行こう!」
セティは子供に応じ、ティニーの手を取り、立ち上がった。
「セティ様・・・・はい!」
そしてティニーもセティに従って立ち上がった。
二人は子供たちともう一度楽しむために、子供たちの中に走っていった。
そしてバーハラ城では・・・
ユリウスとイシュタルの二人に、一つの結末が訪れようとしていた。
イシュタルはユリウスと共に夕食をとった後、どこかに行ってしまった。
ユリウスは食事の後にイシュタルと談話したかったため彼女を探しに出かけた。
イシュタルの自室や他に行きそうな場所を巡ってみたが、それでも見つかりはしなかった。
彼は最後に庭園を捜索することにした。
夜の庭園にいるとは思えなかったが・・・
だが・・・
「あ、ユリウス様!」
イシュタルの声が庭園に響く。
(?・・・イシュタル?)
夜の庭園を照らしているのは天空に広がる星空だけであった。
その中でイシュタルはバラやカトレアといった美しき花達を彩った花壇の中にいた。
(何度見ても・・・本当に綺麗だな・・・花畑にたたずむイシュタルって・・・)
何度も、ユリウスはイシュタルをこの花畑で見つめ、何度も同じ感想を抱いた。
幼い頃も、成長した後も・・・
イシュタルは美しい・・・
(そのことには・・・変わりはないんだな・・・)
「イシュタル、どうしたんだい?ここに来ていて・・・」
ユリウスも茂みへと入り、座っていたイシュタルの隣に腰を降ろした。
「星を見ていたんです・・・ほら、空一面にあんなにたくさんの星が広がって・・・」
イシュタルは満面の笑みで夜空を見上げていた。
ユリウスはそんな彼女をじっくりと見つめた。
表情は透き通るような笑みを浮かべていた。
あまりに透明感に満ちた笑顔は、何かを神秘的なものを連想させる。
彼女の白い肌がこの暗闇の中で星が発する光に照らされ、暗闇の中でまるで宝石セレナイトのように輝いていた。
(美しいな・・・本当にイシュタルは・・・)
今までに何度も感じたことだが、今日は特段にその思いは強かった。
(今日の・・・イシュタルは・・・・今までのイシュタルの中で一番美しい・・・一番綺麗だ・・・)
イシュタルの中に、今までとは違うものをユリウスは感じていたのかもしれない。
「ユリウス様?」
「えっ、なんだい?」
ユリウスがイシュタルに見とれていたのを知ってか知らずか、イシュタルはユリウスの顔を、その綺麗な瞳で見つめていた。
「やっぱり・・・この庭園は綺麗です。花も木々たちも、みんな・・・昼も夜も、別の顔になって、別の美しさを醸し出している・・・本当に綺麗です。」
イシュタルは立ち上がって、周りを見つめる。
本当に嬉しそうな顔をして・・・
(本当に綺麗なのは・・・君だよ、イシュタル・・・)
イシュタルの笑顔・・・
ユリウスにとってこれ以上美しいものなど思いつかなかったし、あるとも思えなかった。
「私・・・ここでユリウス様と出会ったのですね・・・」
イシュタルの呟きに、ユリウスは思わずうろたえた。
「ここで・・・私はユリウス様と出会って・・・ユリウス様と話をしたり、木に登って遊んだり、花畑でお昼寝をしたりして・・・」
イシュタルは昔の事を思い出す。
ユリウスとのかけがえのない日々を。
「そして、私はこの場所で・・・ユリウス様の事を好きになりました。」
「・・・それは僕も一緒だよ。僕は君とここで出会って・・・本当にイシュタルの事を好きになったんだ。」
ユリウスもイシュタルも自分達の大切な時間の情景を頭の中に思い浮かべていた。
遊んでいる光景、笑い合っている光景・・・
そして互いの別れの時に初めて想いを伝え合った時の光景を・・・
「ユリウス様・・・私・・・ユリウス様の事を愛しています・・・」
もう一度、自分の気持ちを伝えるイシュタル。
昔のユリウスの姿を今のユリウスに合わせて・・・
「大好きです・・・ユリウス様・・・」
「・・・僕もだよ・・・イシュタル・・大好きだよ。」
ユリウスも過去の自分と今の自分の気持ちを重ね、イシュタルにもう一度思いを伝えた。
「本当にイシュタルの事が好きだよ。君がいれば・・・なにもいらない。なにも欲しくないよ・・・」
ユリウスはイシュタルに抱き締める。
ギュ・・・と強く抱き締め、イシュタルの存在を自分の内に収める。
「イシュタルさえいれば・・・僕は・・・」
ユリウスの何度も彼女に・・・そして自分自身に言い聞かせる。
「・・・ユリウス様・・・私・・・信じていいんですよね?」
ユリウスの手の内にあるイシュタルは静かに呟く。
顔をあげ、ユリウスに覗き込む。
「ユリウス様のお気持ち・・・本当に信じていいのですね。私の事を好きと言ってくれたユリウス様のお気持ちを・・・」
イシュタルは真剣な眼差しを見せる。
ユリウスはその眼差しを向けられ、再び彼女の事を綺麗に思った。
もちろん、イシュタルを想うユリウスの気持ちに嘘はなかった。
「・・・信じてくれていいんだよ。僕は本当にイシュタルの事を愛しているのだから・・・」
ユリウスはしっかりイシュタルの目を見つめて言った。
「・・・ありがとうございます・・ユリウス様・・・」
イシュタルはユリウスの胸板に埋めながら彼の気持ちに感謝をした。
そして彼女もユリウスの背中に手を回してしっかりと抱き締めた。
しばらく、二人は抱擁し合っていた。
愛する者の体温を肌で感じながら、自分の心が温かくなっていくのを感じていた。
「本当に・・・私は幸せです。私は・・・こんなに幸せで・・・いいのでしょうか?」
イシュタルはユリウスの胸に顔を埋める。
ユリウスの胸の感触を忘れないために。
(僕は・・・イシュタルに幸せを与える事ができたのだろうか・・・?)
ユリウスは、自分の存在でイシュタルに幸せを与える事が出来たかどうか自問した。
これだけ優しく、美しく、健気な少女に・・・
自分のような存在がそんな彼女に幸せが与える事が出来たのだろうかと・・・
だが、その疑問は自分がイシュタルを愛する気持ちの前に消え去った。
(本当に・・・エゴだよな・・・相手の気持ちの事も考えず、自分の気持ちに正直になってしまうなんて・・・)
だが、それほどまでにユリウスはイシュタルの事が好きだったのだ。
「イシュタル・・・僕は君に幸せを与えてあげられたかどうか分からない・・・でも、イシュタルの事が大好きという気持ちだけは本物だよ・・・それだけしか、僕は君に与えるものはないけど・・・」
「ふふっ・・・ユリウス様・・・分かっていらっしゃらないのですね。貴方のその気持ちこそが、私の幸せの源なのですよ・・・」
イシュタルの抱き締める力が強くなる。
「ユリウス様・・・私の事を・・・愛し続けてくださいね」
「・・・もちろんだよ。僕はイシュタルの事を愛し続ける・・・ほかになにもできなくて・・・ごめんね・・・」
イシュタルの気持ちに応えられないと思い込んでいるユリウス。
「・・・なにもできなくなどありません・・・ユリウス様・・・一つ、お願いをしてもいいでしょうか・・・?」
イシュタルは顔を上げ、ユリウスを覗き込んだ。
「お願い?」
「はい・・・大それた願いかもしれませんけど・・・私・・・わたし・・・」
「イシュタル?・・・」
イシュタルは一呼吸置いた。
自分の落ち着かせるために、自分の気持ちを整理するために・・・
「私を・・・ユリウス様の妻にしてください・・・」
運命の一言を、イシュタルは言った。
「妻?・・・それって、僕の妃になりたいってこと?」
突然のイシュタルの申し出に、さすがのユリウスも驚いた。
「・・・はい・・・」
イシュタルの美しい目に涙が浮かんで来る。
表情も悲痛なものに変わってきた。
(イシュタル?・・・君は一体?)
ユリウスはイシュタルの中に、何かを感じ始めていた。
何かとは言えない。
イシュタルがユリウスに結婚を申し込んだことに、彼は何かの想いを感じていた。
それはイシュタルの愛であることはユリウスも分かっている。
だが、それ以外の想い・・・
イシュタルは様々な想いに満ちて、ユリウスに申し込んだように感じられた。
それが何か、今のユリウスには分からなかった。
「ユリウス様と結ばれたいのです。それが、私の夢だったのです・・・ユリウス様を好きになってからの・・・」
ユリウスの中の違和感を消え去ってはいなかったが、それでもイシュタルに気持ちがもたらすものによって自分の心が温かくなっていくのを感じていた。
心地よいこの感覚の前にユリウスは違和感と言う名のわだかまりを忘れていった。
ユリウスの中で大きくなっていくイシュタルへの愛おしさ・・・
ユリウスはイシュタルの愛に、イシュタルへの愛に、正直に動いていた。
「イシュタル・・・ごめんね・・・」
「えっ?」
彼がいきなり謝罪の言葉を発したことに、イシュタルは心が一瞬凍るようだった。
「君の方から・・・そんな勇気の必要な事を言わせてしまって・・・」
「えっ?・・・うっ!?」
ユリウスはそう言うとイシュタルの唇を奪う。
意表をつかれたイシュタルは思わず驚き、目を大きくする。
しばらくユリウスは唇を重ねた後、再び向き合いイシュタルに語りかける。
「僕は・・・小さい時から思っていた事があるんだ・・・イシュタルをお嫁さんに出来たら・・・どんなに嬉しいだろう、って・・・」
「ユリウス様!?」
もう一度、ユリウスはイシュタルをしっかりと抱き締める。
「本当に・・・僕なんかで良いんだね?イシュタルの気持ちを受け取っても良いんだね・・・?」
「・・・ユリウス様じゃなきゃ・・・嫌です。私は・・・ユリウス様と結ばれたいのですから・・・」
「イシュタル・・・ありがとう・・・」
二人の愛が一つの形になろうとしていた。
「イシュタル・・・僕は誓う。君への愛が永遠である事を・・・」
「ユリウス様・・・私も誓います。私はユリウス様を愛し続けると・・・」
月夜に照らされた二人の影が一つに重なり、そして・・・倒れていった。
二人の初夜が月夜の花畑で過ごされようとしていた。
二人は花畑の中で横になっていた。
互いに抱き合いながら舌を絡め合い、口内を堪能するほどの濃いキスを交わす。
唾液を湿らせてのキスは舌と唇を動かすたびに、ピチャ、ピチャとした音を発する。
その音に互いの体が発する男と女の匂い、周囲に咲くカトレアの柔らかく、濃厚な優雅な香り、バラの爽やかながらも刺激的な香りが加わり、さらに二人の気持ちを高ぶらせていく。
「・・・ピチャ・・・うん・・・うあ・・・」
イシュタルは既にキスだけでも感じ始めているようだ。
一旦、キスを中断し、潤いと艶の入った目で相手を見つめ合う。
「・・・はあ・・・イシュタル・・・」
ユリウスも、自身の頭の中が白く霞んでいくのを感じていた。
イシュタルの体と香りを前にしてだからだろうが、それ以前に、本当の意味でイシュタルと結ばれる事が出来て気が高ぶっているのかも知れない。
もう、恐れることはないのだ。
イシュタルは本当に自分の事を愛してくれているのだから・・・
「ユリウス様・・・あっ・・・」
イシュタルがユリウスに言葉をかけようとした途端、彼に胸を掴まれてしまう。
服の上から優しく胸を愛撫していく・・・
「く・・ふぁ・・・あぁ・・・」
ユリウスは力強くならないように、また、彼女の胸の弾力を楽しむように指を食い込ませていく。
「きゃう・・・う・・・はぁ・・・」
イシュタルのいつも通りのスリットの入った、そして大きく胸元の開いた黒いドレスを着ている。
その胸元がユリウスの手の平によって歪む。
「これが・・・あんっ・・・私達の結婚式なのですね・・・」
イシュタルは胸だけでも、発する言葉が虚ろになるほど感じている。
そんな状態でイシュタルは結ばれる喜びを感じていた。
「そうだよ・・・これが僕達の結婚式だよ・・・」
ユリウスはイシュタルの言葉に答えながら、首筋に舌を這わす。
うなじを舌が上下し、淫らな唾液の線を描いていく。
「ふふっ・・・花畑での結婚式・・・とてもロマンチックですね・・・あ・・・」
「そうだよ・・・僕達はここで出会ったんだ。この場所こそ・・・僕たちの誓いの場所に相応しいよ・・・」
二人は互いの体を絡み合わせながら、この瞬間の大切さを噛締めていく。
ユリウスの手はイシュタルの胸や腰に廻され、擦り・・・彼女はユリウスの首に手を回して離さなかった。
「う・・・は・・・せっかくの結婚式なのに・・・こんなに黒い服で迎えることだけが、少し心残りですけど・・・」
イシュタルは黒い服のまま、この幸せの時間を・・・この自分にとって最高に幸せの一瞬を過ごすことに引け目を感じていた。
だが、ユリウスにとっては今のイシュタルの姿も十分過ぎるほど魅力的だと思っていた。
「そんな事はないと思うけど・・・今のイシュタルの姿はとても魅力的だよ・・・」
ユリウスの指が、ぷっくりと隆起した乳首を捉えた。
「ひゃん!・・・でも、一応、私も女の子です・・・」
「イシュタル?」
乳首を弄ばれているため徐々に声に艶が入ってくる。
「私も・・・うあん・・・あ・・・私も綺麗はドレスを着て、ティアラやヴェールで飾って・・・好きな人との愛を誓い合いたかったです・・・ああっ!・・・」
自分なりの夢を、一人の少女としての誓いの儀式での情景を思い浮かべてきていたのであろう。
(イシュタルも・・・女の子なんだよな・・・人並みの・・・女の子らしい)
たが、ユリウスは気づいた。
(何考えているんだ!?僕は・・・イシュタルは元々心優しい、普通の少女だ!普通の女の子のような夢を持って当然ななんだ。彼女のそんな夢をもてないようにしてしまったのは彼女の王族としての地位が・・・そして、僕が彼女を支配しようとしたから、彼女を普通とは違う女性とならなくてはならなかったんだ・・・)
ユリウスは首を振り、イシュタルに失礼な思いを抱いてしまった自分を恥じた。
そんな様子をイシュタルは見ていた。
「ユリウス様・・・どうされました?」
ユリウスは頬を赤らめながらも、自分を心配そうに見つめるイシュタルにときめいた。
ユリウスを見つめるイシュタルの表情はとても愛らしかったから・・・
(せめて・・・イシュタルの些細な夢を叶えてあげたい・・・)
その思いがユリウスにある行動を取らせた。
ユリウスは愛撫を一旦止め、イシュタルの服に手をかけた。
「えっ?・・・ユリウス様?」
イシュタルの黒きドレスを淡々と脱がしていった。
肩口を逸らし、腰を浮かせ、ゆっくりと脱がしていく・・・
イシュタルはその間、抵抗らしい抵抗を見せなかった。
抵抗する理由はなかったし、いずれ脱ぐことになると思っていた。
そして彼女を完全な裸身にしてしまった。
いきなりのユリウスの行動と裸身にされたことにイシュタルが耳まで赤くなった。
「ごめんね・・・イシュタル・・・今の僕の手元にはウェディングドレスはない。君の夢を叶えてあげることはできない・・・だから・・・」
そう言いながら、彼は自分達の周囲にたくさんある花を摘みだした。
赤いバラや白いカトレアなど、色とりどりの花を集め、それを彼女の体に置き始めた。
快感と興奮の汗は詰まれた花達と体を結びつける役目を果たし、その体を花で覆っていく・・・
「ユリウス様・・・これは?」
彼女の髪に赤い花を彼女の体を白い花をメインに彩っていく。
彼女の体の殆どを花で飾った時、まるでそれは花で作られた純白のドレスのようになった。
「だから・・・花のドレスじゃダメかな?この庭園の綺麗な花たちで君を彩るのは?」
ユリウスはそう言いながら自分が彩ったイシュタルの姿を見つめた。
自分とイシュタルを幼い頃から見つめてきた花たち・・・
その花達の中で契りを交わし、その花たちがイシュタルの体にドレスを形作る・・・
そして、あたかも花と同化した感のあるイシュタルの裸体は清らしさと美しさと・・・白とピンクの入り混じった淫らな色気の霧を立ち込めさせていた。
子供の頃にユリウスはイシュタルを花の妖精と形容した。
だが、今の美しいイシュタルの姿は花の女神と形容する事が出来るだろう・・・
「花が・・・私の体を・・・」
イシュタルは自分の姿を見つめ、顔を赤らめた。
恥ずかしい気持ちもある。
だが、自分の大好きな花たちが自分のウェディングドレスになってくれている・・・
花と同化し、その美しさが、その香りが、彼女の心を温かく燃えさせる。
「ユリウス様・・・とても嬉しいです。まるで、花たちにも祝福されているみたいで・・・」
「イシュタル・・・喜んでくれるの?嬉しいよ・・・とても綺麗だよ。今のイシュタルは・・・本当の意味での花嫁だね。」
「そうですね・・・あ、くぅ・・・」
言葉が終わらぬ内に彼女の声は喘ぎに変わった。
ユリウスの愛撫が再開されたからだ。
花に覆われた胸や太股を優しく擦る。
ユリウスの指にイシュタルの体は過剰に、敏感に反応した。
「ああぁ!・・・・や・・・う、うはっ!・・・」
引きかけていた熱が体に戻りイシュタルは悶える。
先ほどより感じているイシュタルの姿を見ると、どうやら裸になったことと、花による香りが彼女の感度と気持ちが高めているみたいだ。
「凄く感じているね・・・イシュタル・・・」
彼の舌が花と花の合間をなぞり、彼女の体を舐めていく。
肩から降りていき彼女の柔らかい丘に近づいていった。
「すごい・・・私・・・あん!感じる・・・頭の中が白くなってくる・・・」
押し寄せる快感のためか、彼女の体は止めどない汗を溢れ出していく。
そして、さらに湿り気を帯びた彼女の体は強く花と結びついた。
快感に揺れる体は花をも揺らし花びらや花粉を撒き散らし始めた。
さらにイシュタルの体が花と香りにまみれていく・・・
ユリウスのイシュタルの胸を丹念に責め始めた。
純白彩られたイシュタルの胸を舌で愛し、手の平で優しく包み込む。
「ふぁあぁぁ・・・あん・・あふ・・・」
ぺろぺろと舌の先が、ピンクの頂を突く・・・そして刺激された頂はさらなる刺激を要求するかのように隆起し始める。
尖った乳首を舌が舐め上げる。
その度にユリウスの唾液が線を空に描き、見るものに淫らな印象を与える。
「ユリウス様!・・ああぁぁ・・・あん!」
イシュタルの声が大きくなってきたのを確認したユリウスはさらに激しくイシュタルを愛す。
左手と舌で胸を責めて、右手は徐々に下半身に向かって動いていく。
腰を擦り、太股を擦り・・・徐々に円を描くように彼女の大事な部分に近づいていった。
「イシュタル・・・感じる?」
優しい愛撫を続けながらユリウスは問い掛ける。
イシュタルは快感の波に震えながら・・・
「ふふっ、私が・・・あ、ユリウス様に愛されて・・・感じない事なんてないですよ・・・うんん!」
ユリウスに応えた。
「女の子は・・・好きな人といるだけで・・・優しい言葉を掛けられるだけでも・・・感じるんですよ。心が温かくなるんです・・・心と体・・・一緒に・・・」
イシュタルはそう言いながらユリウスを強く抱き締める・
「?・・・なに?」
「ユリウス様・・・私を強く愛してください!体と心・・・私の全てに貴方を刻み込んでください・・・」
熱い吐息を出しながらのイシュタルの懇願・・・
快感のために虚ろな瞳になりながらも、瞳の中の光は強い意思を灯していた。
「・・・もちろんだよ。僕はイシュタルを愛する。いくらでも愛してあげるよ。」
ユリウスはもう一度イシュタルに熱い口づけを交わす。
自分の愛する気持ちを相手に注ぎ込むかのように・・・
ユリウスは口づけを交わしながら、自分の右手を彼女の股間に潜り込ませた。
潜り込ませた右手に熱い湿り気を感じる。
既に彼女の女性の部分は蜜を大量に含んでいたのであった。
「イシュタル・・・もう、こんなに・・・」
「あ・・・いや・・・」
「ふふっ・・・可愛いね・・・イシュタルは・・・」
赤くなるイシュタルを笑顔で見つめながら、ユリウスは彼女の秘部を擦り始めた。
「!・・ああぁ!」
今までより甲高い声を発するイシュタル。
「可愛いよイシュタル・・・声も・・・全てが・・・」
ユリウスは十分潤っていたそこに人差し指を突き入れた。
「ううぅぅっ・・・!」
彼女は自分の中に侵入してくる指を感じながら、自らの体がブルブルとするのを感じていた。
彼女のそれはユリウスの待ちわびていたかのようだった。
指を入れられたと同時に彼女の体に電流のような刺激が走る。
彼女の体は求めていたものを与えられはじめ、燃え上がるように熱くなっていった。
指がニチャニチャと彼女の中を掻きまわす。
その度に溢れ返った蜜が流れ出していく。
「イシュタル、聞こえるだろう?君のここ・・・こんなに濡れて、いやらしい音を出しているよ・・・」
「あん!・・・ああぁ!・・・はあぁ・・・」
「ふふ、蜜がたくさん出ているよ。僕の指も、周りの花も、イシュタルのお尻もてらてら濡れてしまっているよ・・・」
ユリウスは指の動きを円運動から突き入れる動きに変えた。
ジュボジュボとイシュタルの中に打ち込まれていく。
先ほどよりも多い量の蜜が垂れ流される。
「あん!ああぅん!・・・あ、ひゃあぁ・・・」
彼女は顔を振り秘所から全身に伝わっていく刺激に反応していた。
ユリウスはさらに指を二本に増やし、彼女の中を掻きまわす。
さらに親指は彼女のクリを回すように擦り、刺激し始めた。
「!?・・・ああぁぁっ!!」
ビクンと跳ねるように彼女が激しく震えた。
「・・・イシュタルって、どこも敏感だね・・・」
ユリウスはさらに手の動きを早いものにした。
胸を揉む力と彼女の女性の部分を弄るスピードを早くして、激しく彼女を悶えさせようとする。
「あ・・・かあぁぁ!・・・ゆ、ユリウスさま・・・あ・・・」
激しくなっていく彼の手つきにイシュタルもさらに声と反応を大きくしていく。
溢れる蜜は女性の香りを醸し出し、周りの花の香りと合い重なってさらに二人を燃えさせた。
「あん・・・あ、あ・・・ああっ!!・・・ユリウス様!私・・・」
イシュタルの中に埋め込まれている二本の指が緩やかに締め付けられる。
どうやら彼女は既に高みに昇りつつあるらしい。
「イシュタル・・・もう、イキそうなんだね?」
「ああ!・・・ふぁあぁっ!・・・ユリ・・・ウスさまぁ・・・」
「我慢することないよ・・・僕に全てを委ねて・・・」
ユリウスはイシュタルの背中に左手を回し、自分の体を重くならないように押し付けて、しっかりと抱き締めた。
そして右手で彼女の花園を愛することに専念する。
片方の手でもしっかりと自分を抱き締めてくれる手の存在に安心したのか、イシュタルは快感の渦に飲み込まれ熱にうなされるようになっていたが、それでも安心した表情を浮かべた。
ユリウスに自分の全てを・・・体や感覚と言った部分の全てを委ねたのだ。
全てを託したイシュタルはユリウスにされるがままに声をあげた。
「ああぁ!わああぁっ!・・・あ、うあああぁぁ・・・!」
・・・チュク!クチュ!・・・チュクチュク!・・・
ユリウスの二本の指がさらに速さを増して動く。
単調な挿入ではなく、指を曲げて、彼女のGスポットも巧みに刺激した。
さらにクリトリスを擦る親指も、押し、転がすような動きに変えた。
二つの性感帯を責めたて彼女を昇らせていく・・・
「あ!・・・あああぁぁ・・・く、かああぁぁ・・・」
「イシュタル・・・」
そして、彼女の体と膣が激しく震え、彼女の花は大量の蜜を噴出した。
「・・・あああうううぅぅぅ・・・!!」
ユリウスは自分の指が締め付けられるのを感じた。
イシュタルは達したのだった。
「・・・はぁ・・・はぁ・・・」
数瞬の痙攣の後、彼女は激しい息遣いをし始めた。
汗が体を覆い、その体を覆う花に染みていく。
「イシュタル?・・・イシュタル?」
激しく息を漏らすイシュタルにユリウスは優しく呼びかける。
「は・・・ユリウス・・・さま?」
達したばかりの虚ろな目でユリウスを見上げた。
「・・・気持ち・・・良かった?」
(なんて情けない質問だ・・・)
ユリウスはあまりに情けない質問をしてしまった自分が恥ずかしかった。
「・・・はい・・・とても・・・」
恐らく意識も濁っていた部分もあるだろうが、それでも出来る限りの笑顔を見せた。
花の群れの中に現れた笑顔・・・
ユリウスにはそれが霞んで見えた。
まるで、夢の中にいるかのように・・・
夢の中で妖精と出会えたような、そんな感覚さえ覚える。
だが、イシュタルは少し膨れた表情を見せた。
「でも、ユリウス様・・・少し酷いです。」
「え?」
いきなりのイシュタルの言葉にユリウスは戸惑いそうになった。
「私ばかり・・・感じさせて・・・恥ずかしい姿を晒してしまうなんて・・・」
そう言いながらイシュタルはユリウスの股間に手を伸ばしていく。
ズボンの膨れた部分を指で擦るように・・・手の平で覆うように・・・
「あ、イシュタル・・・」
イシュタルの悶える姿を見ていた彼の股間はこれ以上ないほど大きくなっており、イシュタルに触れられたことにより思わず甘い感覚がユリウスの中を駆け巡る。
「ふふっ・・・ユリウスさま・・・こんなに大きくしてしまって・・・」
イシュタルは反撃に転じた。
ユリウスの愛撫によって散々燃えさせられてしまったイシュタルは大胆になったのかもしれない。
彼女はユリウスを地面にゆっくりと倒していった。
そしてユリウスの上に重なる。
その間ユリウスは先ほどのイシュタルのしていた表情とは違う・・・子悪魔的というのだろうか?その表情にユリウスは戸惑い、動けなかった。
イシュタルはユリウスの下半身に体を正対させ、彼のズボンの膨らみを見つめる。
(本当に・・・大きい・・・)
イシュタルはあまり手馴れていないのか、ゆっくりと時間を掛けてユリウスのズボンから彼のいきり立ったモノを露出させた。
「ユリウス様・・・こんなに大きくしてしまって・・・」
彼女はユリウスのペニスに手を当てた。
「・・・くぅっ!」
イシュタルの手に捕まれ、ユリウスは思わず反応してしまう。
(手だけでも・・・こんなに反応するのか・・・?)
慣れない手つきで彼女はユリウスのペニスを擦っていく。
実はイシュタルは今までの情交の中でも手と口による愛撫は苦手だったのだ。
何回も行ってきたし、何度もユリウスの射精を促してきたのだが、イシュタル自身は上達しているとは思ってはいなかった。
いや、ペニスを手や男のモノを愛撫するということに慣れていなかっただけなのかもしれない。
事実、ユリウスはイシュタルの行為にとても感じていた。
すぐに出してしまいたくなる衝動に駆られるぐらい・・・
「イシュタル・・・感じる・・・感じるよ」
仰向けにされ、ユリウスはイシュタルの行為を受け入れていた。
彼は今までイシュタルを抱くときにはあくまで自分がリードをしてきた。
そのため、イシュタルの方から自分の意思でこの様に愛撫してもらえる経験は殆どなかったのだ。
(イシュタルも・・・こういうことをしてくれるんだ。愛し合えるとはこういうことなのか・・・)
ユリウスは再びイシュタルと愛し合える関係になった事を感謝した。
その合間にもイシュタルは控えめながらもペニスに指を滑らせていった。
そして、何度か彼女の手の平が何度が上下に往復した後、彼女は恐る恐る舌を出して、ユリウスの先端に這わした。
「あぐぅ!」
ユリウスの背筋を甘いが激しい電流がひた走る。
イシュタルはそれに構わず、目を閉じながらペニスの亀頭をチロチロと舐め始めた。
「あ・・・くぅ・・・」
ユリウスのペニスがさらに大きさと硬度を増す。
イシュタルの舌の動きが速くなり、亀頭の部分だけではなく裏筋もしっかりと愛し始めた。
ユリウスの体に汗が浮かび上がってくる。
彼の体がイシュタルの与えてくる激しい快感の刺激の前に熱くなってきているからだ。
しばらく彼のペニスの周りを舐め回した後、彼女は口を大きく開いて竿を咥えた。
「うっ・・・んんっ・・・」
彼のそれはこれ以上ないほど大きくなっており、彼女の口に納まりきるかどうか心配に思われた。
だが、彼女は喉まで届くほどのユリウスをイシュタルは何とか受け入れた。
そして彼女は噎せ返るような衝動を押さえ込み、愛し始めた。
「うわ・・・あ、イシュタル・・・」
今までよりも一回りも二回りも大きい快感がユリウスを直撃した。
ユリウスは一瞬にして頭の中が真っ白になりそうになった。
イシュタルはユリウスを咥えたまま、前後運動を開始した。
ニュ・・・チュパ・・・ピチャ・・・
「ん・・・うん・・・ふぁ・・・」
息苦しそうにしながらも、イシュタルはフェラを続ける。
口を前後させ、時には動きを止めて舌で包み込んだ亀頭を舐めてみる。
さらに休みになっていた手も、再び上下させ、口と同調した動きでペニスを刺激する。
「う!・・・か・・・くぅ・・・」
「うん・・・チュ・・・んんっ・・・」
激しい快感の波に、今度はユリウスが翻弄させられていった。
ユリウスは自分自身の事が分からなかった。
何度もイシュタルの口に自分のモノを奉仕させてきた。
彼はイシュタルの口や舌の心地よさを知っているはずだった。
だが、今の自分はどうか・・・
イシュタルの能動的な愛撫を受け、これ以上ないほど感じてしまっている。
自分の体が制御できないと自覚させられるほどに・・・
自分が変わってしまったのか?それともイシュタルが変わってしまったのか?
あるいは両方なのか・・・?
イシュタルは自分が、この様な奉仕といった類の事が苦手だという自覚があったのかもしれない。
彼女は今までユリウスの言うとおりにしていれば良かったのだから。
でも、今は自分からユリウスに尽くしたかった。
だが、いざ自分から行動するとなると彼を上手く感じさせられるかどうか分からなかった。
それでも尽くしたいという気持ちの一点のみのために、彼女は精一杯に彼のモノを愛したのだ。
それが返ってユリウスに至上の快感を与えているのかもしれない。
ユリウスは自分の股間に顔を埋めているイシュタルを見つめた。
花を着飾った女神のような美しさを持つ少女が自分のモノを愛してくれている。
これだけの清い心と容姿を持った少女が自分のモノを淫らな愛撫してくれる。
そのミスマッチがユリウスをさらに熱くさせてしまう。
程なく、ユリウスは射精感が込み上げてきた。
「ダメだよ・・・イシュタル・・・もういいよ・・・」
ユリウスはこのまま放つつもりはなかった。
彼はイシュタルの中で果てたいと思っていたからだ。
その声にイシュタルは一旦動きを止めて、上目遣いでユリウスの顔を見つめた。
一瞬、二人の間に静寂が訪れる。
だが、イシュタルは再び口と手の動きを再開した。
しかも、先ほどよりも速く、激しい動きで・・・
「あく!・・・イシュタル・・・ちょっと・・・」
ユリウスは思わぬイシュタルの行動にうろたえながら、身震いをした。
ユリウスは彼女を静止しようとした、だが、彼女はさらにユリウスに対する責めを激しくした。
そのため、ユリウスは込み上げてくるものを押さえることはできそうになかった。
「おい・・・く、か・・・」
「ん!・・・うん!・・・うう・・・」
イシュタルはがむしゃらにという表現が正しいようフェラを続ける。
そのためにユリウスはあっという間に昇らされてしまった。
「く、わあああぁぁぁぁっ・・・!!」
イシュタルはユリウスのペニスが手の中で、口の中で脈動するのを感じた。
そして、イシュタルはユリウスの白濁した熱い欲望を口内で受け止めた。
彼女の喉を彼の精液が打つ。
勢いが強かったことと、その独特の異臭のために噎せ返りそうになる。
だが、イシュタルはそれを我慢して彼にペニスから口を離し、その熱い液を一呑みにした。
「んん!・・・く、くはっ・・・」
最後の一滴を飲み干そうとした時、彼女の喉はついに悲鳴を挙げて噎せてしまった。
少量の白い液が咳と共に吐き出され、彼女の唇から垂れていく・・・
その光景にユリウスは射精のためにぼんやりとしていながらも、再び胸とペニスが熱くなるのを感じていた。
美しいシルバーブロンドに花を飾った美少女が自分を向きながら、精液を口元から零しているのだ。
彼の欲望を満足させると同時に肥大させるに十分だった。
「ユリウス様・・・いかがでしたか?」
少し、心配そうな表情で彼女は尋ねた。
恐らく自分がユリウスを気持ち良く出来たかどうか疑問だったのだろう。
だが、ユリウスにとっては愚問であろう。
さして時間が掛からず、果てさせられてしまったのだから。
「はぁ・・・気持ち良かった。」
半ば、興奮状態のユリウスは、その一言しかいえなかった。
一旦、呼吸を整えてから、もう一度イシュタルに答える。
「本当に気持ち良かった・・・怖いぐらい、感じたよ・・・」
ユリウスは今までにない高ぶりを感じていた。
イシュタルはその答えを聞いて、笑顔を見せた。
「良かったです・・・私・・・ユリウス様を尽くす事ができたかどうか心配で・・・」
ほっとした感じであった。
「でも、いきなりビックリしたよ・・・イシュタルの方からこういう事をしてくれるなんて・・・」
ユリウスはイシュタルの行動に驚いていたのだ。
ユリウスの言葉にイシュタルは顔が真っ赤になった。
「ごめんなさい・・・私・・・ユリウス様に愛されて・・・昇らして頂いて・・・気が高ぶってしまって・・・」
少しイシュタルは俯いた。
だが、俯いてもイシュタルの耳がこれ以上ないほど赤くなっているのが分かる。
「高ぶってしまって・・・ユリウス様ともっと激しく感じ合いたいと思って・・・思わず、ユリウス様を尽くしたいと・・・」
「イシュタル・・・」
「ごめんなさい・・・勝手な事を・・・」
「イシュタル・・・一つだけ・・・」
ユリウスはそう言いながら、再びイシュタルを優しく押し倒した。
花畑に再びイシュタルの体が沈む。
「あっ・・・」
「こういう事をされて・・嫌な気分になる男はいないよ・・・」
優しい声で囁きながら、彼は両手を彼女の下半身に走らせた。
「今度はイシュタルの番だよ。また、イシュタルを気持ち良くさせてあげる・・・」
ユリウスは彼女の足を両手で大きく開き、先ほど散々弄った花園を見つめる。
「さっきよりもね・・・」
そして、ユリウスは彼女の花に舌を這わせた。
瞬間、彼女の体がこれ以上ないほど跳ねた。
「ひゃん!!」
舌が彼女のクリを一舐め舌だけだった。
だが、既に十分過ぎるほど熱く高まっていた体はあまりに敏感だった。
指でクリトリスの包皮を捲り、現れた果実をむしゃぶるように音を立てながら嘗め回す。
ジュルジュルとわざと音を立てて、クリを口で刺激した。
その度にイシュタルの体が驚くほど跳ね続ける。
先ほどからの一連行為で散々なまでに愛液を垂れ流した彼女の秘所から、再び愛液の分泌が始まる。
「イシュタル・・・すごく濡れているよ・・・」
「いや・・・あ、ああぁぁん!」
クリを舐めるたびにトロトロと流れ出す蜜は、地面へと落ちていく。
ユリウスはその光景を見て、惜しそうな表情をする。
「もったいないな・・・イシュタルの美味しい蜜が・・・無用に流れちゃうなんて・・・」
彼はクリから口を離し、代わりに左手の指で果実を弄ることにした。
空いた口は零れ続ける蜜を舐めとることにした。
花に口を合わせ、クリの快感によって流れ続ける蜜を音を立てて吸い続ける。
・・・ジュルジュルルル・・・ズズ・・・
「う!・・・うん!ひゃあぁぁっ・・・」
「美味しい・・・イシュタルの・・・」
まるでユリウスは美しい花に群がる蜂のように、それを求め続ける。
クリを左手で刺激するだけでなく、右手を長く伸ばして彼女の胸を揉み回す。
「もっと・・・奥まで・・・」
ユリウスはさらに舌を彼女の中に挿し入れた。
そこで微妙に震え、また、彼女の膣壁を舐めあげる。
彼女の性感帯という性感帯を刺激し続けていく。
あまりの快感の渦に、イシュタルはたちまち昇らされてしまいそうになる。
腰の震えが止まらなくなっていく・・・
「ひゃ・・・あああぁぁっ!だ、だめえぇ・・・頭が痺れちゃう・・・」
腰をヒクヒクさせるイシュタルに、ユリウスはゆっくりと顔を上げていく、
「イシュタル・・・」
全身を悶えさせ、激しい息遣いになっていたイシュタルは赤くなった顔をユリウスに向けた。
潤んだ瞳で・・・放心したかのような表情で・・・
「ユリウス様・・・もう、わたし・・・」
ユリウスは優しい笑みを浮かべながら囁いた。
「何を求めているの?・・・ちゃんと聞かせて・・・君の口から・・・」
「あ・・・ユリウス様・・・」
潤んだ瞳は十分に何を求めているが物語っていたが、ユリウスは言葉にして欲しかった。
「私・・・あの・・・その・・・」
イシュタルが自分から切り出せないのはいつものことだった。
何度も抱かれてきたはずなのに、イシュタルのその初々しさは、いつまでも消えることは無かった。
「ちゃんと言って・・・イシュタル・・・じゃないと、いつまでも・・・」
そう言いながら、ユリウスはイシュタルの秘所をクチュクチュと掻き回す。
僅かな意地悪さがイシュタルを追い詰める。
「・・・いつまでも・・・このままだよ・・・」
「ああっ!・・・あ・・・んんっ!・・・ひゃ・・・」
激しく、指でイシュタルを悶えさせるユリウス。
一段と激しく彼女のGスポットをなぞりあげた後、動きを止めた。
「イシュタル・・・欲しいのだろう・・・?」
「・・・ぁ・・・はぁ・・・ぅは・・・」
ユリウスの声はあくまで優しく、囁きかける様であった。
「我慢しなくていいんだよ・・・」
「ユリウス様・・・私・・・」
イシュタルはユリウスの首に手を回して、ギュと抱き締めた。
「お願いです・・・私・・・ユリウス様が・・・」
「なに?」
「・・・ユリウス様が欲しいのです・・・愛してください・・・」
「うん」
イシュタルのお願いにユリウスは応えるべく、体を起き上がらせた。
そして、自分の気持ちをイシュタルに沈めていった・・・
「はあああぁぁっ・・・!!」
イシュタルは自分の中を進んでくるユリウスを感じて声を出した。
彼女の花は待ちわびていたものを受け入れ、これ以上ないほど悦び、快感に打ち震えていた。
そしてユリウスのペニスも彼女の花の温かさと心地よさのために、甘く激しい波となって脊髄に直撃する。
ユリウスはさらに腰をゆっくりと突き出す。
自分とイシュタルをさらに深く、さらに強く一つになるために。
「ああぁ!・・・はぁ・・・はぁっ!・・・」
「イシュタル・・・また、一つになれた・・・」
何度も体を重ねあった二人だが、ユリウスはこの瞬間、一番の安らぎを感じる事が出来た。
イシュタルと自分が身も心も一緒になれたと信じられる、この瞬間こそが・・・
イシュタルは挿入されただけでこれ以上ないほど体が熱くなり、そして感じていた。
自分の中に進入したペニスのせいで感じている事もあるのだろうが、何より、ユリウスと一緒になれたこと、そしてこれから愛し合える喜びを考えただけで、イシュタルの体は高まり、熱くなっていった。
これだけ、自分がこれだけ熱くなれるほど愛する事が出来る人がいることに幸せを感じながら・・・
そして、この愛する人と契りを結ぶ事が出来て、本当に良かったと思っていた。
自分は最高の幸せを手に入れたのだから・・・
互いの潤んだ視線が重なり合い、どちらからともなく頷き合った。
そして、ユリウスは動き始める。
「あっ!・・・あん!・・・あああぁぁっ!・・・」
イシュタルは声を抑えることなく、感じたままに素直な喘ぎ声をあげた。
一回の往復でイシュタルは頭の中が真っ白になるような、そんな感覚に襲われた。
ユリウスも熱い、激しく締め付けるイシュタルの中に、我を忘れて突き入れてしまいたくなる衝動に駆られた。
愛する人の体を欲した二人は、激しく相手を抱き寄せる。
互いの胸と胸が重なり合い、二人は性器だけではなくなく、全身で一つになった。
「イシュタル・・・動くよ・・・」
その言葉にイシュタルは頷いた。
頷いた彼女の目は閉じられていて、目尻から一筋の涙が零れていく。
そしてユリウスにも聞こえないような小さな声を呟いた。
「・・・私に・・・思い出をください・・・」
「あああぁぁっ・・・!はあああぁぁっ!ゆ、ユリウスさまあぁっ・・・!!」
「イシュタル・・・イシュタル!!」
激しい息遣いと喘ぎが辺りにこだまする。
ユリウスはイシュタルの背中に、イシュタルはユリウスの首に手を回しながら、激しく動いていた。
ユリウスは力一杯、イシュタルを貫いていた。
恐らくイシュタルにはそれなりの苦痛も感じているだろう。
だが、それ以上の快感の渦がイシュタルを包んでいた。
洪水のような蜜を流し、ユリウスを受け入れていた。
グチョグチョとした水音が挿し込まれるたびに鳴り、行き場を無くした愛液が溢れかえってくる。
激しく揺れる二人の体は周囲の花も靡かせていた。
色とりどりの花びらたちが夜の闇に舞う。
ユリウスとイシュタルはまるで理性を忘れたかのように互いの体を求め合っていた。
「うううぅぅっ・・・!!・・・うはっ!・・・ああ・・・!」
イシュタルの喘ぎはさらにユリウスの欲情を刺激して、一段と激しく動かす。
彼女の体が弾けて行ってしまうかのような激しい突き上げであった。
だが、二人は相手の体をしっかりと抱き締めていたために、二人の距離が離れることはなかった。
ユリウスもイシュタルも愛しい人を抱き締めていたかった。
離したくはなかった・・・この温もりを、この大切な存在を・・・
だが、今の二人は確かに傍にいた。
結ばれているのだ。
だから、結ばれている喜びを今は何よりも噛み締めていたかった。
「ユリウス様!・・・もっと、強く・・・強く愛してえぇっ・・・!」
イシュタルは全身を弾ませながら、美しい髪を揺らしながら哀願していた。
大量の涙がイシュタルの美しき顔を濡らしていた。
「ああっ!・・・愛して・・・私を愛してください!・・・私に貴方を刻み込んで!!」
涙に濡れるイシュタルの顔は美しいと思いながら、ユリウスは彼女に応えた。
「いくらでも愛してあげるよ・・・いくらでも僕を刻み込んであげる・・・」
「・・・う、うれしい・・・くっ!?・・・ああ!!」
言葉だけではなく、ユリウスは行動によってもイシュタルに応えた。
一段と激しい、子宮にも届くかのような激しく突き上げた。
イシュタルの中に自分を刻み込むかのような熱く、強く貫いていく。
イシュタルは挿し込まれる度に喘ぎ、悶えた。
ユリウスの与えてくる快感と自らの高まりが引き起こす疼きによって、挿し込まれる度にオーガズムを迎えているような錯覚さえ覚えた。
いや、もしかしたら本当に昇りつめているのかもしれない。
あまりの性感のためにイシュタルの体は終わる事のないスパークに見舞われていたのだった。
「あああぁぁっ!!・・・うわああぁぁっ!・・・ゆ、ユリウス・・・ユリウスさまああぁぁっ!」
既に狂乱状態のイシュタルは自分の胸に顔を埋めるユリウスの頭を力一杯抱き締めた。
思わずユリウスは息が詰まり、窒息するかのような思いをした。
何とか顔を横に向け口を解放した後、大きく息を吸った。
その後、再び激しくイシュタルを愛す。
「もっと・・・もっとおぉ!!・・・あああぁぁっ・・・!!」
「はっ!・・・んんっ!・・・イシュタル・・・」
二人は限界へと近づいていった。
ユリウスは自分の先端に耐え切れない存在が込み上げて来ている事を、イシュタルは今までとは比べ物にならないほど大きな衝撃が近づいてきている事を悟った。
さらに相手も自分と同じように限界に近づいていることに・・・
「ダメ!・・・くる・・・おかしくなる!・・・やあああぁぁっっ・・・・!!ユリウス様!!」
「イシュタル・・・僕も・・・もう・・・」
互いの動きが最高潮に達しようとしていた。
ユリウスは来るべき爆発を迎えるべく、最後のスパートを掛けた。
彼のペニスはこれ以上ないほど肥大していた。
逆に彼女の膣は収縮をはじめ、彼のペニスを締め上げた。
二人が限界に近づいている事を物語っていた。
「ユリウスさまああぁぁっっ!!もっと、もっとおぉ・・・!」
イシュタルはユリウスを包みこみながら、ひたすら叫んだ。
「もっと強く愛してええぇっ!!私が貴方を忘れないように・・・強く・・・強くうぅっ!」
イシュタルその叫びには、何か、彼女の思いが込められているようだった。
あまりに悲しく、せつない思いが・・・
ユリウスにもイシュタルのその声が聞こえていた。
だから、彼女を力強く、壊れるぐらいに愛した。
自分の気持ちを叩きつけようとした。
それが彼女に応える唯一の方法なのだから・・・
「イシュタル!・・・受け取ってくれ!!僕の気持ちを!!」
彼のペニスが一番深い所まで挿し込まれ、そこで震えた。
白く熱い思いをユリウスはイシュタルの中に放った。
イシュタルは自分の中の奥底に叩きつけられる精液を受け止めた。
「!?・・・うううぅぅ・・・あああぁぁぁっ・・・!!」
そして彼女も極限の状態を迎えた。
ユリウスの愛をその身に受けて・・・
「・・・はああああああぁぁぁぁっっっ・・・!!!」
痙攣する体、極まった喘ぎ声と表情・・・
彼女は愛する人に数瞬遅れて昇り詰めた。
「・・・ユリウス・・・さま・・・わたしは・・・」
彼女は白き世界に落ちていく瞬間、大切な人の名を紡ぎだした。
自分の想いを遂げられた喜びに満ちながら・・・
二人はこの初夜を通して晴れて結ばれることができた。
夫妻としての契りを交わすことができたのだった。
(・・・・・・?)
次にイシュタルが目覚めた時、彼女の視界にはたくさんの色とりどりの花の姿が入ってきた。
ぼんやりとした意識の中でも、黄色のフリージアや薄桃色のゼフィランサスの美しさに心奪われる。
自分が別の世界、夢の世界に入り込んだのかも知れないような気さえしてしまう。
「イシュタル・・・気がついたの?」
突然、自分を呼ぶ大切な人の声が聞こえてきた。
振り向くと、自分のすぐ横にユリウスの姿があった。
自分とユリウスは庭園にある大木に寄りかかるように座っていた。
二人は裸のままであったが、今の二人の体はユリウスの着用していたマントに覆われていた。
どうやらユリウスは気を失ったイシュタルの肩を抱き、ずっと一緒にいるみたいだった。
「私は・・・気を失っていたんですね・・・」
「うん・・・大丈夫?・・・」
ユリウスにしても、あまりの高まりに気を失ったイシュタルの事が心配でならなかった。
ユリウスが自分を心配してくれる事が、彼女には嬉しかった。
この闇の神に心囚われた少年は、自分にだけは優しくしてくれる・・・
自分と一緒にいる時だけ、本当の姿に戻ることは出来るのだ。
それだけ自分の事を優しくしてくれる事がイシュタルにとっては幸せだった。
「私は大丈夫です・・・ごめんなさい。あれだけ乱れてしまって・・・」
「何を言っているの?好きな女の子が乱れる姿を見て、嫌な男なんていないよ・・・」
自分の乱れ振りを思い出し、また、その姿を相手にじっくりと見られてしまったことに、彼女は顔を赤くした。
顔を赤くするイシュタルの肩を抱き、自分の体のほうに抱き寄せる。
イシュタルの銀髪のロングヘヤーの心地よい香りを感じながら、二人の体は密着した。
「可愛い・・・僕のイシュタルが可愛く、激しく・・・悶えてくれたんだから・・・」
「・・・ユリウス様の・・・いじわる・・・」
ちょっとだけ、頬を膨らますイシュタル・・・
その子供のような姿にユリウスはイシュタルとの時間や距離を取り戻したような気分になれた。
しっかりとイシュタルの肩を抱き、夜空に広がる数多の星を見上げた。
戦時下にもかかわらず、星の光は輝いており、月と共に暗闇の中の庭園を照らしていた。
「綺麗な・・・空だね・・・」
「本当に・・・」
イシュタルもユリウスの向く先に気づいたのか、同じように夜空を見上げ、その美しさに目を奪われる。
今までに何度もこの輝く星空を見上げてきたはずであったが、今ほど、この光景に心ときめかせた事はなかった。
自分達の心の安らかさ、気持ちが、改めてこの素晴らしき光景を際立たせているのかもしれなかった。
「まるで・・・私たちの事を祝福してくれているみたいですね。星たちや、草花たちが・・・」
「そうだね・・・私たちが結ばれる事の祝福をしてくれているようだ。」
今の二人にはこの見慣れた風景、何度も見上げた星空が自分達の幸せを象徴しているように見えていた。
ユリウスもイシュタルも、今、最高に幸せを感じていた。
最愛の相手と結ばれた喜び・・・
今、二人は晴れて結ばれた。
互いに誓い合った仲になったのだ。
幼い頃に知り合い、想い合い、数多の障害を乗り越えて、二人は結ばれる事ができた。
過去のことなど関係ない、未来の事など今は考えない・・・
今、この一瞬が二人の幸せなのだから。
「私・・・こんなに幸せに・・・自分がこれほど幸せな気持ちになれるなんて・・・思いもしなかったです。」
イシュタルの目尻に光り輝く雫が浮かんで来る。
彼に寄りかかり、彼の肩にそっと、頭を置く。
そんなイシュタルの肩を、ユリウスはしっかりと抱き締めた。
「僕も・・・幸せだよ。大好きなイシュタルと、こんなに心が通じて愛し合えるようになったんだから・・・」
「ユリウス様・・・」
ユリウスにとっても、イシュタルにとっても、一番の望みは最愛の相手と一緒になることだった。
それが今まで、二人が望もうとした・・・紆余曲折と誤解、すれ違いはあったものの、それを二人は望んで、ここまで来たのだ。
「私達・・・・やっと、ここまで来れたのですね・・・」
「イシュタル?」
「色々とありましたけど・・・やっと、素直な気持ちで、ユリウス様と向き合えるように、ユリウス様と愛し合えるようになったんですね。」
イシュタルは一言一言、噛み締めるような感じで話していった。
「ユリウス様に優しく愛されて、私はユリウス様への想いをより強くする事が出来ました。そして、ユリウス様は私を妃にしてくださいました・・・私の願いが叶ったのです。」
イシュタルの笑顔で言葉を続けた。
彼女は今、本当に幸せだった。
自分の全ての想いが果たされたのだから・・・
もう、なにも心残りはなかった。
「ユリウス様・・・ありがとうございます。私の願いを叶えてくださって・・・」
イシュタルは顔をユリウスを見上げ、今までにない明るい声で、明るい笑顔で言った。
大粒の涙を流しながらも、その笑顔は輝きに満ちていた。
彼女の幸せな気持ちを表現するかのように・・・
「私・・・幸せです。最高に幸せなのです。私は今、自信を持って言えます・・・自分がこの世界で一番幸せな女だって・・・誰よりも、心を満たす事ができたって・・・」
「イシュタル・・・」
「だって、ユリウス様の妻になる事が出来たのですもの・・・自分の望みが叶ったのですから、もう、なにも望むことなんてありません・・・」
(イシュタル・・・君はそこまで僕の事を・・・こんな僕なのに・・・)
彼女の事をユリウスは愛していた。
その気持ちに嘘はない。
だが、自分はイシュタルに酷い事を行ってきた。
暗黒神にまで魂を売った。
そんな自分の事を信じてくれる・・・
そこまで自分を愛してくれる・・・
(イシュタルは僕に誓ってくれた・・・だから、僕も誓いたい・・・)
ユリウスは何を思い立ったのか、ゆっくりと立ち上がった。
立ち上がったユリウスをイシュタルは見上げた。
「ユリウス様?」
「少し、ここで待っていて・・・」
ユリウスはイシュタルを制しながら、庭園の奥に向かって歩き出した。
彼の姿が闇に溶け、しばらくイシュタルは一人になってしまった。
しばらくすると、イシュタルの元にユリウスは戻ってきた。
彼の手にはイシュタルにも見覚えがない一輪の花が握られている。
白い五枚の花びらが広がった小さな花で、華やかさはないものの、十分に可愛らしい花であった。
イシュタルも立ち上がって、ユリウスの傍に駆け寄る。
「ユリウス様・・・その花は?」
イシュタルの問いにユリウスは答えた。
「この花はジャスミンって言うんだ。とても良い香りがする花で、香水や薬などにも使われているんだけど・・・」
そこまで喋った後、ユリウスの顔はとても赤くなった。
少し恥ずかしそうな感情がユリウスの口調に混ざる。
「ある本で読んだんだ・・・ほかの大陸のことだけど、恋人たちの中でこの花を贈ることは変わらない愛を相手に示す事だって・・・そして、贈られた相手がそのジャスミンを髪に飾ってくれたら、それは互いの愛が不変である印にするって・・・」
「えっ・・・?」
「イシュタル・・・君にこの花を捧げる。僕の愛を示すために・・・だから、君の・・・この花を神に飾ってくれるかい・・・?」
ユリウスは自分の気持ちが不変である証明をイシュタルに渡したかったのだ。
体の結びつきだけでもなく、夫婦としての契りだけでもなく、自分の気持ちを花に託して・・・
イシュタルは目を閉じ、一呼吸を置いて彼の手からジャスミンを受け取った.
「イシュタル・・・」
そして自分のシルバーブロンドにジャスミンを飾ったのだった。
「ユリウス様のお気持ちを・・・ありがたく・・ううっ・・・」
突如、彼女の言葉と笑顔が崩れた。
大粒の涙が彼女の頬を伝う。
「ううっ・・・受け取らせてください・・・そして、これを私達の愛の印にする事をお許しください・・・」
彼女は全身を震わせながら最後まで言葉を続けた。
そして、ユリウスに抱きついた。
ユリウスはそんなイシュタルの言葉と行動に頷いて、飛び込んできた彼女を抱き締めた。
「ユリウス様・・・」
「イシュタル・・・」
二人はしばしの抱擁を交し合った。
イシュタルはユリウスの胸の中で震えながらも彼の背に回した両手にしっかりと手を入れる。
二人は互いの体が壊れるのではないかと思うほど強く抱き合った。
「イシュタル・・・愛しているよ・・・」
「私もです・・・ユリウス様・・・」
今までにない幸せに包まれながら、二人は見つめ合った。
そして目を閉じて、二人は唇を合わせあった。
深く、長いキスを・・・
そして、もう一度見つめ合った。
辺りには夜風とそれに靡いた草木の擦れる音のみが響いていた。
そんな中で、イシュタルは言葉を出した。
「・・・ユリウス様・・・これだけは信じてください・・・私はユリウス様を愛していると・・・たとえ、何があっても、私のユリウス様への気持ちに嘘はないと・・・」
ユリウスはイシュタルの言葉に頷いた。
もう、ユリウスは彼女の事を疑うことは出来なかったし、必要もなかった・・・
「僕はイシュタルを信じるよ・・・たとえ、何があってもね・・・いや、そんな事なんて考える必要もないか・・・僕達はこれからも、ずっと一緒なんだから・・・」
「・・・そう・・・ですね・・・」
イシュタルは再びユリウスの胸に顔を埋め、その中で泣いた。
ユリウスにはイシュタルのその行為が感極まったためだと思っていた。
「イシュタル・・・もう、部屋の中に帰ろう・・・明日のために、今日は寝よう・・・」
「・・・はい・・・」
二人はユリウスの部屋で休むべく、そろって歩き出した。
イシュタルの肩を抱き、二人は共に歩いていった。
ユリウスはこの時、限りない未来を信じていた。
確かに、今は戦争が続いているが、それも自分にある忌まわしき力があれば負けることはない。
そして敵がいなくなり、彼の気に入らない人、国、世界を滅ぼした後、イシュタルと幸せな生活を送れると信じていた。
信じていたのだった・・・
そのような未来が来る事を・・・
しかし、その未来が来ることはなかった・・・
ユリウスが自分の寝室で起きた時、すでに昼過ぎになっていた。
恐らく、今までにない充足感を感じていたユリウスは安心して眠っていたのかもしれない。
そして、彼が遅めの眠りから覚めた時に彼女の新妻となった少女の姿は目の前から消えていた。
「イシュタル・・・?」
彼は眠気が完全に抜ききれないままであったが起き上がり。彼女の姿を探した。
だが、彼の部屋の中にも、外に突き出しているベランダにもイシュタルの姿はなかった。
(どこに行ったんだ?イシュタルは・・・)
彼は部屋の中で右往左往していた時、部屋の中央にあるテーブルに手紙らしき物があることに気づいた。
「これは・・・?」
一枚の紙には見覚えのある筆跡でメッセージが書かれていた。
『ユリウス様、お許しください。私は早朝出撃するヴァイスリッターと共に戦いに行ってまいります。貴方のもとを去る事をお許しください。
私はユリウス様をお救いすることはできませんでした。ユリウス様が苦しまれていた時、私はユリウス様をお傍にいる事も、守ることもできませんでした。そのためにユリウス様はロプトウスにさせてしまったのです。
私がお傍にいればユリウス様を守れたかどうかは分かりません。でも、守りたかった、貴方の心の支えになって差し上げたかった。そうすれば、ロプトウスの魔の手から貴方を守る事ができたかもしれないのに。
貴方の優しさを、貴方の笑顔を奪い去ったのは私なのです。貴方を好きと自分で言っておきながら、貴方に何もして差し上げる事が出来なかった、最低な女なのです。
だから、私は罪を償います。貴方を苦しめ、救えなかった罪を償うことにします。ユリウス様、本当に申し訳ありません。
最後に、昨夜、私の我儘をお聞き入れくださり、本当にありがとうございました。ユリウス様の妻になるという私の夢を叶えてくださって。そして私の気持ちを満足させて頂いて、本当に幸せです。
これで私には心残りはありません。心置きなく、貴方をお守りするために戦うことができます。私はユリウス様の妻として、ユリウス様への想いを胸に立派に戦ってまいります。
ユリウス様、今まで本当にありがとうございました。
そして、ごめんなさい。
さよなら、私の愛したユリウス様・・・』
最後にはイシュタルの名が滲んで記されていた。
恐らく、手紙の最後の方は涙を流しながら書いたのだろう。
「そんな・・・そんな!」
手紙を持つユリウスの手が激しく震えた。
彼はこれ以上なく混乱していた。
「どういうことなんだ!?」
彼は絶叫を上げたため、部屋中に彼の声が響いた。
(どうしてなんだ!?イシュタル・・・どうして、戦いなんかに行ってしまったんだ!どうして僕の元から離れていってしまったんだ!昨日、せっかく僕達は結ばれたのに・・・やっと、君と素直に愛し合えたのに・・・どうして・・・)
彼の脳裏に昨日のイシュタルの様子が思い浮かぶ。
彼女の告白と願い、彼女と愛し合った時の事、そして、彼女にジャスミンを贈った時の事・・・
既にあの時、彼女は決心していたというのか?
ユリウスの元から離れる事を・・・
だから、彼女は最後の願いとして、最後の思い出として、昨日は共にしたというのか?
(僕は・・・結局、何も分かってはいなかったんだ・・・)
結局、自分はイシュタルの事は何も分かってはいなかった。
何も理解してあげることはできなかったのだ。
彼女が悩んでいる事も分かってあげられなかった。
自分だけが愛し合えた事に浮かれ、彼女の本当の気持ちを見過ごしてしまった。
(もう、イシュタルとは会えない・・・イシュタルと会えないんだ。)
彼の元からイシュタルは去った。
その事実を突きつけられたのだ。
だが、彼女への怒りを感じることはなかった。
全ては彼女の決心を、いや、気持ちを理解してあげる事ができなかった自分のせいなのだから・・・
「・・・ごめん・・・イシュタル・・・」
(全ては・・・僕のせいなんだ・・・)
「イシュタルゥゥ―――――ッ!!!」
バーハラ城とフリージ城を結ぶ街道は山脈の合間に存在していた。
この狭い山間において、一つの戦いが起きようとしていた。
フリージ城から出撃した解放軍とバーハラ城から出撃したヴァイスリッターの両軍が正面から遭遇したのであった。
バーハラ攻略を目指す解放軍には主力が終結しており、その中にはティニーやセティがいた。
今、彼女達はこの戦いを最後の戦いにするべく、気合に満ちていた。
そして帝国軍ヴァイスリッターの戦列に、一人の少女の姿があった。
早朝、ユリウスの部屋から抜け出し、出撃する帝国軍に混じってきたイシュタルであった。
彼女は様々な決意を秘め、解放軍との戦いに臨もうとしていた。
グラン歴778年初頭・・・
解放軍のイザークでの蜂起から始まった一連の戦い・・・後に『聖戦』と言われる戦いは、12聖戦士の家に連なる者や多くの人々を引き裂き、戦いに巻き込んでいった。
その中で、互いに信じあった従姉妹達がいた。
イシュタルとティニー・・・
同じフリージ家の人間として生まれ、共に育った彼女達は、互いの事を大切に思い合っていた。
相手の事を誰よりも知り、思い出を共有し、助け合った彼女達の絆はなにより深いものであっただろう。
そして今、絆で結ばれていた二人にとっての聖戦が始まろうとしていた。