「なぁ、コータ」
「んー?」
呼ばれてオレは気のない返事をした。だらだらと歩く見慣れた道。隣にはいつも通りにアイツがいる。
でも街はいつもとちょっと違う。色とりどりのLEDに、赤い服の店員。手に手をとって歩く人たちは、そんな街の気分に明るく照らされている。
「なんでクリスマスまで練習あるんだろな、ウチの部は」
「いいじゃん、青春賭けてますーって感じするよ」
「ハハ、なんだそれ」
他愛のない会話が続く。
「どうせ今日しかグラウンドがとれなかったとかそーいうんじゃないの?」
「あー、うん、ソレありえる。ヤグチさん押し弱いから」
「誰よヤグチって」
「マネージャー、1コ上の」
そんな会話も、横断歩道の雑踏で人をよけた拍子に途切れたりする。二人組が小走りでオレたちの間を通っていった。大通りをにわかに吹き抜ける風に、オレは思わず身をすくめる。
「でもお前はさ、今日なんもなかったろ。昼間どっか行ったりしねぇの」
後ろからアイツが聞いてくる。
「別に…」
「ふーん、そっか」
「クリスマスがどーのってはしゃぐようなガラでもないし」
階段を登ってゆくと、少し街のざわめきが遠くなる。歩道橋の上には、古ぼけた蛍光灯の光だけがあった。
にわかに静かになった感じがして、オレはあわてて話を続けた。
「オマエだって、そんなにはしゃいだりしないだろ」
「ん、まぁなー。少なくともアレだ、ブカツして帰るだけのクリスマスじゃあな」
「…だからオレが来てやってんじゃん…」
ボソッと言ってしまってから、ハッとして立ち止まった。
気がつくと、オレはすっぽりとアイツの腕の中におさまっていた。温かな重みが背中を包む。
「なんだよ、やめろよ」
「いいじゃん、クリスマスなんだから」
頭も目も手足も硬直したまま、ただ感情がオレの全身を浸潤していく。
しばらくして、アイツは小さなため息をひとつ。それから少し腕の力を緩めて、あやすみたいにオレの肩を数回なぜた。
「やっぱクリスマス好きだわ、オレ」
「言ってること違うし」
「だってさー、こーいうことしてもオマエ怒んねぇし」
急にちょっとだけ低くなった声に、オレはドキリとした。耳元でそれはズルイ。
「怒って、怒ってるだろ、てゆーか、」
「あーもぉうるさいって」
アイツはまた少し、腕に力をこめる。吐息は、ぬるま湯みたいにオレの首をすべっていった。
「…今日だけだかんな…」
下を向いて、オレは小さく言った。
「オマエのそーいうとこも好き」
「なっ…やっぱダメ!もうはなせよ!」
「んだよ、ケチだな、ケチ〜」
オレは耳まで真っ赤だったに違いない。ふり返るのも恥ずかしくて、早足で歩道橋を渡りきると、そのまま階段を踊り場まで下りていった。見下ろす車道には、赤いテールランプの列。それを見つめて少し待っていると、パーカーのポケットに両手をつっこんだアイツが下りてきた。
オレとアイツは、またにぎやかな雑踏の中に戻っていた。
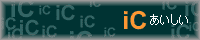 iC / あいしい(作者サイト)
iC / あいしい(作者サイト)

