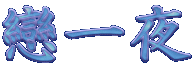
終章
恋しけば 形見にせむと わが屋戸に 植えし藤波 今咲きにけり
---- 山部赤人
その家の庭に、この花が植えられていることに気付いたのはいつのことだろう。
進藤ヒカルは、見事な藤棚を見上げていた。
今が盛りと咲く紫と白の藤は、五月の風に揺らめく。もの言いたげに見えるのは、藤という花の名前のせいだろう。そう思って、ヒカルは苦笑いしながらも、その場所から離れられずにいた。
それにしてもこの色の取り合わせ…。思い出さずにいられない二つの色。
「呼びだてておいて、待たせてすまない」
縁側から声がして振り返る。塔矢行洋が開け放たれた障子に手を掛け、静かに立っていた。その気配にすら気付かないほど、自分は藤に見入っていたのかと、ヒカルは驚く。
「いえ、そんな…」
「まあ、上がりたまえ」
招き入れられたその部屋は、ヒカルが一度も入ったことのない塔矢行洋の居室だった。塔矢アキラと親しくなってから、何度もこの家には来ているが、こうして行洋に呼び出されたのは初めてのことである。
庭から部屋に上がり、勧められるままに座布団に正座する。そうして庭をふと見たときに、藤棚がこの部屋から一番よく見えるように植えられていることに気付いた。
「…先生は藤…お好きなんですか…?」
この人の前にいると、いつまでたっても小さな子供のような気分になる。ヒカルはもうすぐ成人を迎えようかという自分の、おどおどした口調に困惑したような表情を浮かべた。
「そうだな、好きな花だ」
緊張した面持ちのヒカルを、さして気にもとめないように行洋は一瞬藤棚に目をやってから、僅かに口元に笑みを浮かべてそう言った。その柔らかな面差しに、ヒカルは複雑な感情が生まれてくるのを感じていた。
なんといっても、今日、自分を呼び出したのは、他ならない塔矢行洋自身だった。アキラは今日は地方の対局に出かけている。アキラのいない日に、自分を呼び出したのか、それとも唯の偶然か。それすら問いただすこともできない威圧感を、行洋は保持している。これこそいくつものタイトルを制覇し、保守してきた気迫。
ヒカルは自然とまっすぐに伸びる背筋を感じていた。
「別に藤を見せようと呼び出したわけではなかったのだがね…」
屈託なく笑いながら、行洋はヒカルの前に碁盤を運んできた。
「うわっ、先生すみません…」
塔矢行洋の居室に入って、一局打たないなどということはありえないのに、自分は対局準備もしないで、うっかり勧められるままに座り込んでしまった。それにやっと気付いたヒカルは慌てて立ち上がろうとした。
「いいんだいいんだ」
笑顔のままでヒカルの動きを制して、行洋は碁笥を二つとも自分の横に置いた。
「…え?」
てっきり碁笥のひとつは手渡されるものだと思い、差し出そうとしていた手が空振りする。驚いた表情のヒカルを、行洋は静かに笑って見た。
「皆のふがいなさに、私がもう一度プロ試験を受けて戻ろうかと思ったこともあったほどだったけれど…」
碁笥の蓋をゆっくりと開いて行く。
「それも大人気ないだろうと思い、黙って見ていることにした」
黒石も、白石も、自分の手元に置いて。
ヒカルはまだ驚いた表情のまま、行洋を見詰めるだけ。
「…本因坊、おめでとう、進藤君」
静かな祝辞とともに、行洋はまっすぐにヒカルを見据えた。その瞬間部屋に風が舞い込んだ。
「今日君を呼び出したのは、その祝儀の為だ」
言いながら、指先が慈しむようにゆっくりと黒石を摘み上げた。
ピシリ。ピシリ。
棋譜を並べて見せるにしてもゆっくりすぎるその動きの意味を掴もうと、ヒカルは食い入るように盤面を覗く。
数手進んだとき、ヒカルは息を飲み込んだ。
「…これは…」
行洋はその問いには答えず、手を進めて行く。ヒカルには答えなど必要ないと、知っていたから。
ゆっくりと、並べられてゆく美しい絵。
その棋譜に息づく懐かしい面影。
白い指先、長い袖、そして水が流れゆくような石の動き……。
ヒカルはもう何も言えずに嗚咽を堪えていた。
「ズルイや…ズルイや塔矢先生…」
本因坊のタイトルを取ったときにも、泣きもしなかったし、派手に喜びもしなかったと週刊碁の記者が感嘆したように言っていた。
名人位を昨年アキラが取った時には、アキラは泣くまではいかなかったけれど目を真っ赤に腫らしていたのに…と。
けれど今、彼はひとつの棋譜を目の前にして、泣きじゃくっている。
「…あいつと打ったんですね…先生…こんなのズルイや…」
肩を震わせて、ずっと大事に持っているという扇子を握り締めて、ヒカルは止まらない涙をどうにか止めようとして、ひどく咽込んだ。
行洋の目に、碁盤の向こうの青年は、かつて自分の病室に訪ねて来た時と、見損じないほど幼く見えた。
ヒカルの想いのほどを感じて、行洋はしばし黙って見守ることにした。
どれほどの想いで、彼はここまで辿り着いたのだろう。その痛々しいほどの努力を想像すると、「酷なものを幼い者に託したものだ」と、苦笑いとお小言をくれてやりたくなるほどだった。
ふっ…と、小さく口元を緩ませ、行洋は藤棚を見る。
その一瞬、花たちの狭間に、懐かしい面影を見た気がした。
瞳をゆうるりと細める、忘れられないあの笑顔。
「…進藤君…」
驚きのあまり、唇が勝手に動く。ほんの一瞬ではあったけれど、でも。
「はい?」
まだ泣きながら、ヒカルはゆっくりと顔を上げた。その前髪を、ふんわりと風が揺らす。
あまりにも自然に、その不自然な風は存在した。
「…あ………」
ヒカルは瞬きも忘れたように行洋を見上げた。
同じように行洋も、ヒカルを見る。
互いに一瞬だけ、同じものを見たのだと、表情と視線で確認しあった。
「…全く心憎いことだ」
深く吐息をつきながら、行洋は呟いた。けれど言葉とは裏腹に、その表情は穏やかなものだった。
その眼差しの優しさに、何も感じないほど、ヒカルももう子供ではなかった。
「先生…」
もの言いたげな表情に、行洋は最初から答えるつもりもなかったけれど、否定をするつもりもなかった。
「私は約束を果たしたまで。…あれは、藤のほうが勝手に咲いたのだよ」
顎をしゃくって藤棚を示すと、行洋は静かに立ち上がった。
「さて、私は少し席を外そう」
その棋譜をゆっくり見たいだろう?と、言外に匂わせて歩き出す。
「先生」
ヒカルが盤上から目を離さないまま、声をあげた。行洋が足を止める。
「大丈夫、俺、もう十分見せて頂きました」
導く手が見える。
道程を指し示す、白く輝く指先が。
ヒカルはそう思って、笑顔を浮かべて顔を行洋に向けた。
「それより先生、俺と一局打ってください」
そのまっすぐな瞳の中の凛とした強さを見て、行洋は微笑んだ。
「分かった」
碁盤の向こうに座りなおした行洋が、白石を集め始める。それにならって黒石をあつめながらヒカルは悪戯っぽい笑いを向けた。
「ところでこの棋譜…勿論誰にも秘密ですよね?」
慌てたように藤が揺れたことに、残念ながら二人は気付かなかった。
連載前からこの話を見守ってくれていたゆら様に、この終章を捧げます。
危なっかしい御話を見守りつづけてくださってありがとうございました。
<終章あとがき>
終章まで含めて恋一夜です。
ここのためもあって、行洋に佐為が秀策でもあったことに気付いてもらったわけなんですね。
「きたるべき時」を見極めて頂くために。
ちなみに行洋が、自分も本因坊のタイトルを一度くらいは取っておけばよかったって台詞が本編であったんですけど、前後展開が甘すぎてボツにしました。
で、ここで言わせてみようと思ったんですけど、これまたたるくなったんで諦めました(苦笑)
思ったようには、なかなか書けないものですねえ。
この山部赤人の歌は、時代が外れちゃいました。万葉集のもの。
でもなんて都合のいい歌なんでしょう、ビバ!赤人!!
ここではあえて、新章のほったゆみ形式をとらせて頂きました。(意味分かりますよね?)
これはこれで趣のある手法だなあと思いました。
青年ヒカル…書いてて楽しかったですvv
そのうち番外編で補完話書くかも。
天上界編。可愛い佐為を書きたくなったら書くなり。