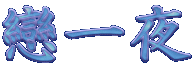
其の参
あらざらん この世のほかの 思ひ出に 今一たびの 逢ふこともがな
---- 和泉式部
碁笥に碁石を収める作業を、これほどまでに用心深く行ったことがあっただろうか。
行洋は何気ない表情を装っている自分の、その意識的な動きに戸惑いながら考える。
碁石のひとつひとつを、慈しむように集めて行く指先の動きに、ともすれば目が行ってしまう。
----当たらないように、あのあまりにも白い指に触れないように。
そう思うあまり、まるで佐為に合わせるように慎重に手を動かしたため、ただ碁石を分けて集めるだけの作業は随分長引いた。
「和泉の歌…私も好きでした」
とても楽しいことのように軽やかな口調で言いながら、佐為の指は碁石を緩やかに碁笥に収めてゆく。
一足先にその作業を終了した行洋は無言で、佐為の研磨されているはずの爪を見ようとしていた。あまりに嬉しそうに碁石を集めてゆくので、本当にこの平安貴族が絵巻から抜けてきたような人物が、あのsaiなのかと首を傾げたくなるほどだったから。
「まっすぐな瞳をしていて…恋をしている瞳そのままで歌を読む、美しい女房でしたよ…。彼女の歌が今の世に残っていることを、あまねく神に感謝したいほどです」
確実に彼を碁打ちだと語る爪先が、最後の石を碁笥に戻す。その指の動きを追うあまり、言葉の後で自分を見つめてきた佐為の視線に、しばらく気付かないほどだった。
「そうして…あの歌を選んでくれたあなたにも」
その透き通るような微笑みは、もう藤原佐為という存在が人でないものになっていることを行洋に教えながら、それでも行洋の、胸の奥底に眠る甘い水を掬いあげるほどの美しさと儚さを孕んでいた。
月明かりは頼りなくはあったけれど、確実に碁盤を照らし、それは言葉でなく灯りを点す必要はないと対局者たちに伝えていた。
「私が握ろう」
行洋が、碁石を一掴みした拳をゆっくり盤上に乗せる。
その様子を柔らかい眼差しで見守りながら、佐為は全身をゆっくりと巡る喜びに目を細めていた。
対峙して碁を打つ。
それを塔矢行洋が、これほどまでに望んでいてくれたということが、たとうべきものもないほどに嬉しかった。
「では…」
緩やかに手を伸ばし、碁笥の中に指を入れる。懐かしい石の感触が、指先に優しかった。
掌に呼び込まれた碁石一つをそっと碁盤の上に置く。
小さな音を立てて佐為の指を離れた黒石を見届けて、行洋は自分の白石達を解放する。
「…私が白ですね」
佐為が呟き、行洋は無言で頷いた。
碁笥を交換し合うと、盤上を照らす月が、束の間雲に隠れた。
双方空を見上げ、小さな雲が流れ行く様を認める。次に盤上が照らされた時が始まりと、暗黙の了解が頷きあう二人の間で成立した。
戦いが、あれほど焦がれ、願い、そして祈りすらした戦いが始まろうとしている。
薄闇の中、探りを入れる視線ではなく、気迫を伝え合う為の視線が行き交う。
空をただ流れ行く雲すらも、時を知る。
夢と現の狭間にて、今咲こうとしている、美しい一局を彩らんと。
其の四
<其の参・備考>
掬い上げる…すくいあげる
孕んでいた…はらんでいた