私の名前は『西塔皐(さいとう さつき)』23歳。
少しだけ恵まれた家庭に生まれ、少しだけ有名な大学を出て、親のコネで少しだけ大きな外資系企業に就職したばかりの、極々平凡で取り柄のないOLです。
地道にコツコツと働いて、行き遅れる前に親か親戚か上司の紹介で見合いでもして結婚出来ればいいなぁと考えていた程度なので、当然、仕事に対しての野心も持ち合わせてはいないし、結婚相手に望む事は平凡でもいいから穏やかに暮らしていければいい程度の収入と容姿だったんです。
なのに。
「おい、皐!コーヒー!」
「は、はい!」
私の名前を呼び捨てにして、横柄に命令をしているのは28歳の若さにして海外事業部マネージャーのフランシス・アクトン様。
名前から丸判りの様に、日本人ではなくアメリカ人なのに日本語も堪能。
金髪で青い目、ハンサムで背が高くて独身で、おまけにCEOの息子・・・だからあの若さでマネージャーになれたと言う人もいるけれど、彼は確実に実績を上げている。
私はそんな彼の秘書。
新卒の新入社員が就く仕事ではないと思うんですけど、何故かご指名を頂き大抜擢。
お陰で、女子社員の皆さまの視線が痛いです。
「お待たせいたしました」
私はアクトン様のデスクにコーヒーを静かに置きました。
どうして上司を『様』付けにするのか?
それは彼の『俺様オーラ』が有無を言わさず、そう呼ばせてしまうので。つい。
流石に本人の前ではそう呼びませんけれど。
「皐、ミルクがないぞ」
「え?」
いつもコーヒーはブラックではありませんでしたか?
戸惑う私に、アクトン様はニヤリと意地悪そうに笑って私の胸を指差した。
「出せ」
セ、セクハラです!いえ、それともパワハラ?
私は顔を真っ赤にしながらも、渋々ブラウスのボタンを外しました。
だって、言う通りにしないと後でどんなお仕置きが待っているか。
はい、お察しの通り、私、アクトン様に既に美味しく頂かれてしまってます。
秘書に手を出す上司だなんて、官能小説の世界の様ですが、本当にあるんですね。
コーヒーと私のミルク(ちなみに私はまだ母乳が出るような状態ではありませんが)を堪能されたアクトン様はデスクとPCに真面目な顔をして向かいながら、まだ少し息が整わない私に指示を出されました。
「企画書の英訳は午後一までに終わらせろ。報告書も今日中にな」
「は・・・はい」
アクトン様は会話は堪能でも漢字が苦手の様で、英訳は秘書の務めです。
幸いにも、私は英語と仏語ぐらいでしたら何とか出来ますので、辛うじて秘書の仕事をこなせている状態です。
「残業は許さんぞ。今日、指輪が出来上がる筈だから受け取って来い」
そう言って投げ出された預かり証。
ああ、やっぱりあれは夢ではなかったんですねぇ。
指輪と言うのは、信じられない事ですが、アクトン様と私の婚約指輪の事なんです。
2週間程前に宝石店へ連行されて作らされたエンゲージリング。
私の誕生石でもあるエメラルドの周りに5つの小さいダイヤモンドをあしらった豪華な指輪。
名前と記念日を掘るのに2週間かかると言われましたが。
ぼんやりと預かり証を眺めるだけで、受け取らない私に焦れた様なアクトン様の檄が飛びます。
「何をボサっとしてる!」
「す、すみません!」
私は慌てて預かり証を受取り、自分のデスクに戻りました。
私、プロポーズされた記憶が無いんですが、このままだとアクトン様と結婚する事になるのでしょうか?
私は先程も申し上げた様に、結婚相手には程々の収入と容姿だけを求めていたんです。
でないと私とは釣り合いませんから。
優しくて誠実そうな人と一緒になれればいいなぁ、と考えていたのですが。
アクトン様では私の考えとは違い過ぎます。
どうして私なんでしょうか?
私は美人でもなく、頭が良い訳でもないのに。
ド近眼なので分厚いレンズの眼鏡をかけているし、髪も長くて黒いだけが取り柄で綺麗に巻いている訳でもなく、少し太めなのでゆったりとした服を着ていたら、アクトン様から身体のラインがビシッと出る様なスーツを着る様にと指示をされました。
お陰で、最近は他の皆さまからの視線が痛いです。
実は下着も指示されてまして、口にするのも恥ずかしいものを身につけています。
アクトン様が何故そこまでされるのか理解に苦しむ所なのですが、それでも彼の指示に従ってしまうのは、あの方が私の上司だからと言うだけではなく、実は・・・恥ずかしながら私もお慕い申し上げてしまっているからなのです。
だって、あの容姿と腰に響く様なバリトンの声で迫られたら・・・女性なら誰だって言う事を聞くと思います。
秘書となって1週間後にベッドに誘われ、1ヶ月後には彼のマンションへと拉致同様に連れ去られ、2ヶ月後の今ではどうやら婚約している模様。
ノーと言えない日本人の私がいけないのでしょうか?
指輪を受取りに行く為に、アクトン様より先に退社する私に、彼の指示が与えられました。
「皐、今日は『赤』だ」
アクトン様の指示通り、私は指輪を宝石店で受け取ってから、彼のマンションへと向かい(今ではどうやら私の家にもなっている様なのですが)、夕食の支度をして、シャワーを浴び、薄化粧をして着替えます。
緋色の肌襦袢へと。
『赤』は緋色の肌襦袢、『黒』はメイド服、『白』は・・・その、エプロンだけなんです。
アクトン様はどうやらコスプレがお好きな様で。
家事をする時以外は、部屋の中で眼鏡を外すように言われているので、彼の表情はよく判りませんが、私が指示された格好でお出迎えをすると、とても喜ばれる様です。
「おかえりなさいませ」
『赤』の時は、髪をゆるく纏めてアップにし、三つ指をついてお出迎えします。
なんだか、遊女になった様で恥ずかしいのですが、慣れとは恐ろしいもので、最近ではあまり・・・夕食後の事を考えれば恥ずかしいとは思いますが。
まあ、その・・・偶に夕食前になる事もしばしばありますけど。
「皐、左手を出せ」
私が受け取って来た指輪をアクトン様に渡すと、彼は私の左手の薬指にそれを填めて下さいました。
ぼやけた視界に輝く緑色の石。
「外すなよ。ずっと填めとけ」
アクトン様のご命令ですが。
「・・・どうして?」
どうしてなのか、私には判りません。
「ああ、家事をする時ぐらいは外してもいいが、会社では外すな」
いえ、そう言った意味ではなく。
「何故、私と急に・・・」
婚約する気になったのでしょうか?
「9月からLBSに留学するからな、お前も一緒に行くんだ」
ええっと・・・LBSとはロンドンのビジネススクールの事ですか?
わ、私も一緒に行くんですか?
「そうだ、2年間もお前をこっちに一人で置いておける訳がないだろう」
危なっかしくて目が離せないからな、と呟かれました。
私、そんなに頼りないのでしょうか?
確かに、最近は流され易い性格かなぁとは思わないではありませんが。
それはあなたが強引過ぎるからでは?
私が訴えかける様に彼をじっと見つめていると、ぼんやりとした視界の中の彼が笑ったように見えました。
「皐、お前はこれからずっと私の傍にいるんだ」
そう言って私を抱きしめてくれました。
私は顔だけでなく、身体まで熱くなって「はい」とだけ答えました。
例え釣り合わない相手であろうと、好きな人に求められるのは幸せです。
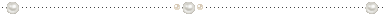
折角、皐が作ってくれた夕食があるのは判っているんだが、婚約指輪を頬を染めて嬉しそうに眺めている彼女を見ていると、この場で押し倒したい欲望を抑え付けるのが大変だ。
何しろ、彼女は私の指示通りに緋色の肌襦袢の襟を大きく後ろに空けて項を露わにし、解れた髪の色っぽさときたら・・・まさに大和撫子!サイコーだ!!
父親の会社に押し込まれて、極東に飛ばされ、不貞腐れていた日々だったが、皐と出会えてからは薔薇色に変わった。
会社説明会に来ていた彼女と偶然ぶつかり、その分厚い眼鏡に隠された素顔を見た時、はっきり言って一目惚れだった。
大きな黒い瞳は神秘的で、長くて真っ直ぐな髪は艶やかで、おまけにそのスタイルの良さときたら。
本人は『太っている』などと言っているが、あれくらいでは太っているとは言わない。
日本の女性は痩せ過ぎている。
肉付きが良くなければ抱き心地だって悪いと言う事を知らないのか?
もっとも、あの眼鏡とダブついた服のお陰で、いらん虫が今まで近寄って来なかったのは不幸中の幸いだったが。
身体に見合った服を着せれば、男達の視線が変わった。
だが、もう遅い。
皐は私のモノだ。
立場を大いに利用して、彼女を私の秘書に配属し、1週間は我慢した。
でも、一週間が限界だった。
あの分厚い眼鏡越しに上目遣いで送られる視線。
ちょっとトロそうな仕草にゆっくりとした口調と丁寧な言葉遣い。
ギャルゲーのキャラクターだって裸足で逃げ出すくらいの可愛らしさだ。
脱がせば、豊かな胸と括れた腰に触り心地のイイ尻に白くてしっとりとした肌。
慣れていない素振りも奥ゆかしくてイイ。
溺れるのに時間は掛からなかった。
本人は自信が無さ気だが、仕事だってキチンとこなす。
私が残業を禁じれば、就業時間以内に終わらせる事も出来るし、決められた期日をキチンと守って仕事を上げて来る。
翻訳の腕も確かだ。
私の秘書として充分に使える。
それに秘書として傍に置けば、今日の様にいつでも触れ合う事が出来る。
コーヒーを運んできた彼女の白いブラウスから下着の色が透けて見えた。
私が買ってやったピンクのレースのブラ。
言えば、恥じらいながらも彼女は胸を曝け出す。
ブラの色よりも淡いビンク色の乳首に吸い付けば、可愛い声で啼くし。
デスクに押し倒してファックするのを我慢するのに、どれほどの努力をしたか、彼女は知る由もないだろう。
でも今は、オフィスではないし、邪魔する急ぎの仕事もない。
夕食は後回した。
私は簪一つで纏め上げてある彼女の髪を解いて、リビングのソファーに押し倒した。
真っ赤に塗ったルージュに唇を合わせて、私だけの遊女に覆い被さる。
「あ、晩御飯が・・・」
皐はそう言って形ばかりの抵抗を試みるが、私に通用しない事も良く知っている。
困ったように眉を下げて、私を見詰める。
可愛い。
その視線がどれほど私を煽っているのか、彼女は知らない。
緋色の肌襦袢の白い襟から覗く胸の谷間、そして下着を着けていないからシルクの生地越しに主張するニップルがくっきりと浮かび上がっている。
触ってくれと言わんばかりじゃないか?
緩く結んであるだけの帯を解いて外すと、シュッと小気味の良い音がする。
「あ・・・」
皐は襦袢で隠されていた肌を露出させられて、恥ずかしそうな声を上げるが、そんな事に一々手を止めてはいられない。
露になった胸を柔らかく包んで舌でニップルを転がす。
昼間も堪能したが、今度はセーブする必要がない。
舐めて甘く噛んで吸い付く。
「やぁ・・・ん・・・」
滾るような欲望を湧き起こす皐の声。
どれ程私を煽るつもりだ。
恥らって染めた頬、伏せた長い睫毛、顔に掛かる絹糸のような黒髪。
サイコーだよ皐。
乳房の輪郭に手を滑らせてからそのまま腰へと下ろして行く。
「皐、脱がせろ」
息が荒くなりつつある彼女の耳元で命じれば、皐は重そうな瞳を開いて震える手で私のネクタイに手をかける。
ネクタイにその細い指をかけて引き緩める。
それからワイシャツのボタンも一つずつ外していく。
緩慢なその動作に焦れてしまいそうになるが、皐の太腿を何度も撫で擦り、その肌の感触を楽しみながら彼女の反応を窺う。
「はぁ・・・んん・・・」
皐の呼吸は次第に速く大きくなっていく。
漏れる吐息は艶めいて益々私を煽る。
「皐、次はどうする?」
シャツのボタンを外し終えた彼女に、何をするべきかを問う。
彼女は俯きがちに恥らいながらも、チラリと私を上目遣いで見てから、スラックスのベルトに手を掛けた。
ファスナーに手を掛ける前に、既にテントを張っている私のモノに躊躇いながらも、そっと撫でる事までやってみせる。
くっ・・・随分と慣れてきたものだな。
既に下着を濡らし始めている私のモノを皐に咥えさせる為に、私はソファーに横になった。
「皐、脚をこっちに・・・」
戸惑っている彼女に、私の顔を跨ぐ様に指示する。
彼女の緋色の着物が私の視界を赤く染め、その中に彼女の白い脚と濡れた花弁が見える。
指をスッと濡れた場所に滑らせると、ピクンと皐の身体が跳ねて、私の太股を彼女の柔らかな髪が擽った。
「あ・・・やっ」
露わにされた私のモノに皐の熱い息が掛かって、私の声も出そうになる。
指で花弁の淵をなぞりながら、人差し指を奥へと忍び込ませる。
グリグリと探れば、皐の声が変わって来る。
「ひぁっ・・・」
ある場所に辿り着いた私の指は、私の上で悶えるだけの皐を責めて蜜を溢れさせる。
「皐、ちゃんと私のモノを咥えろ」
私の言葉に皐はふら付く身体を起こして、私のモノを口の中に射れた。
柔らかく熱い感触に声が出そうになるが、それを堪えるかのように彼女の襞に舌を伸ばす。
「ん、んん〜」
私のモノで口を塞がれている皐も声が出せない。
暫く、そのままでオーラルを楽しむ。
快感に震える皐の舌遣いは絶妙で、堪えるのが大変だったが、私が舌でクリトリスを刺激すると、あっという間に果てた。
ガックリと力が抜けた彼女の口の中に私が放つと、彼女の陶然とした表情に白く掛かる。
そのエロさに、すぐに復活する。
汚れた彼女の顔を拭いてから、中途半端に脱がされたままの服を脱ぎ、寝室へと皐を運ぶ。
初めて抱いてからというもの、離れている時間が惜しくて、一人暮らしの彼女を私のマンションへと住まわせた。
皐は知らないだろうが、彼女の両親にも了解は取ってある。
何しろ、彼女の父親は取引先の重役だ。
機嫌を損ねて引き離されでもしたら困る。
この一カ月の間に着々と準備は進んでいる。
8月末にはロンドンに行かなくてはならないから、それまでに皐のビザを何とかしないと。
いや、やはりビザは無理かな?
今回は観光ビザで行って何度か帰国させるようにするしかないか。
パスポートの名義を変更するのが精々だな。
全く、皐と出会ってからは予定が狂ってばかりだ。
結婚なんてするつもりは全然なかったのに、皐と出会ってその考えが少しだけ変わった。
コイツとならずっと一緒に居てもいいかな?と思って。
でも、結婚はLBSから戻ってからが良いと思っていたのだが、秘書にして傍に置けば手を出さないではいられないし、抱けば片時も手放せないほど可愛いいなんて・・・許せんよな。
皐に内緒で式と披露宴の準備を進めていると知ったら彼女はどれほど驚くだろうか?
クスッ。
ベッドの上で緋色の肌襦袢を纏わせたままの皐はぼんやりとした顔をして私を見上げている。
眼鏡が無くてよく見えないんだろう。
まだ少し赤い頬をそっと撫でて、耳元で囁いた。
「皐、明日、籍を入れるからな」
私の言葉にパチパチと瞬きをした皐は「せきって・・・」と言葉をよく理解出来ていない様だ。
「入籍の事だ」
頬を撫でた手を下へと滑らせて、乳房を軽く握る。
「あっ・・・え?」
快楽と疑問の狭間で戸惑う様子がおかしくて可愛い。
「明日、お前はウエディング・ドレスを着るんだ。私の為に」
そう、だから残念ながら跡は着けられないし、今夜は激しくも出来ない。
「ええ?明日ですか?あ、そんな・・・はぁん」
白い肌に跡は着けられなくても、ニップルなら構わんだろうと吸い付けば、皐は驚いた声の後に可愛い声を上げる。
「嫌か?」
そう言えば、準備に追われて皐に聞いてなかったか?
「え?その・・・私が、ですか?」
「そうだ」
白い肌の上に舌を滑らせながら答えると、皐は身震いをしながら更に尋ねて来る。
「んん・・・その、アクトン様とですか?」
コイツは私の事をまだ『様付け』で呼ぶのか?
「明日からオマエも『ミセス・アクトン』だ。フランシスと呼べ」
お仕置きとばかりに、皐の中に指をグイッと突っ込む。
「ひゃん!は、はい!フランシス様!」
まったく、コイツは・・・だが。
「呼び辛かったら『旦那様』か『ご主人様』でもいいぞ」
ニヤリと笑いながら、ゆっくりとクリトリスを撫で回してやると、敏感になっている皐はピクピクと震えながら叫んだ。
「あっ、ああっ・・・はぁぁん・・・ご主人様ぁ」
うん、その呼び方は萌えるな。
「皐、私と結婚するな?」
彼女の顔を覗き込むように間近で確認する様に尋ねると、定まらない視線を必死で私に向けて頷いた。
「は、はい・・・」
そしてニッコリと可愛らしく微笑んだ。
もう・・・コイツは!
明日の事なんてどうでもいい!
腰が抜けるくらいに突きまくってやる!
唇を覆い被さる様な乱暴なキスをして、脚を広げて持ち上げる。
ゴムなんて着けてる余裕はない!
取り敢えず中に射れさせろ!
「あん、やん、あっ、あっ、ああん・・・は、激し過ぎますぅ」
ここ一カ月の同棲生活で、私とのセックスに慣れて来ていた皐でも、流石に6回連続は堪えたのか、まともに歩く事が困難だった。
仕方無く、私は皐の腰を抱える様にして役所周りをしてから、教会へと向かう羽目になった。
「少しは加減して下さい」
眼鏡を掛けた皐が上目遣いで私にそう文句を言って来たが、そんな仕草は私を煽るだけだと言う事を、その身体でじっくりと教えなくてはならないな。
|